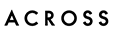子どものころから本がすごく好きでした。本を読む環境が整っていたんでしょうね。本代はお小遣いとは別で、本だけはいくらでも買ってもらえたんです。家には名作全集なんかもあって、谷崎の『細雪』初版本のような超貴重な本が応接室のガラスケースに鎮座していたり。でも、雑誌も好きでしたよ。
実家は愛知県の津島市。駅前に飛鳥文庫という大きな書店があって、そこの常連客でした。僕は小さい頃から書店の店頭にない本を求める子どもで、新聞の広告を見て本屋に行って、店頭にない本は客注していました。客注少年ですね(笑)。本が届いたらいつも、オカンといっしょに本屋に行って買ってもらっていました。
本を好きなだけ買ってもらえたというのは今にして思うとありがたかったですね。自分にも子どもが生まれたばかりなので、同じようにしてあげたいと思います。
本はよく読んでいましたが、運動もしていましたよ。文系な人だと思われるんですけど、3歳から水泳をやっていまして、高校生の時は水泳部主将でした。100m57秒くらいで、当時愛知県で10位くらい。ボーイスカウトもやっていました。アウトドアは好きで、今でもキャンプは好きでときどき行くんですよ。
初めて海外に行ったのは大学1年、18歳の時です。行先はロンドン。ピカデリーラインに乗って、ピカデリーサーカスで友だちと待ち合わせをしたんですが、そこの階段を降りて出た時に「ああ、外国って本当にあるんだな」と感動したのを今でも覚えています。
その時は3週間くらい友人とウイークリーアパートを借りて、ナイトクラブツアーをしましたね。当時はドラムンベースがロンドンでも出たばかりの頃で、GOLDIE(ゴールディ)なんかがまだすぐ近くで回しているのを見られたんですよ(笑)。
ナイトバスを駆使して3週間夜遊びしまくって、昼は美術館。当時は「センセーション」展などが話題になっていて、リアル・ブリティッシュ・アーティストたちが出てきていた頃です。ダミアン・ハーストの大きい作品集(『I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, With Everyone, One to One, Always, Forever, Now』)なんかがちょうど売れていました。
僕は、アートブックをいろいろ買い込んで、日本に持って帰る時にオーバーウェイトになりそうだったので、軍物のズダ袋に入れて機内持ち込みで20kgくらいの本をすっごい軽そうに運ぶ、というのが得意技でした。そのズタ袋は今でも海外買い付けの時とかに使っています(笑)。そうやって買ってきたアートブックは、今でも僕の本棚の重要な一角を占めています。
「幅的お祭りを巡るツアー」から青山ブックセンターへ
大学は法学部の政治学科でしたが、ゼミは文学部の美術美学史科を取っていました。先生は近藤幸夫さんという元国立近代美術館の学芸主任でいらっしゃった、手塚治虫展を初めて国立の美術館で企画されるなど結構ユニークな方でした。ゼミの方が面白くて、一応法学部所属のまま勉強させてもらったんです。
大学卒業後、このまま働きたくないなあと思って(笑)、日本橋郵便局のアルバイトで貯めたお金を握りしめてカナダに留学しました。余ったお金で“幅的お祭りを巡るツアー”というのを勝手に組み立てて、働く前に見ておきたいものを全部、ツール・ド・フランスとかジャズ・フェスティバルとかグッゲンハイム美術館とかアアルトのコエタロなどを、好き勝手にバックパックで見て回りました。
子どもの頃から本がずっと好きだったところに、大学で美術を勉強したことで、アートブックを作るのなんて面白そうだ、という感じで漠然と興味を持っていました。そして旅行から帰ってきて職業を選択しようという時には、何となく本に絡んだ仕事をしたいなと思っていました。小売りでも本を作る側でもよかったんです。
しかし当時は就職は超・氷河期。しかも、僕は就業経験もない。で、困っていたところに、偶然青山ブックセンター(以下ABC)の求人を見て、就業経験なしでも大丈夫ということで、受けたら採用されました。ただ倒産する直前で会社も最悪の状態ですし、コストもカットにカットを重ねているような、大変な状況でしたね。
入社後に配属されたのは六本木店で、建築とかデザインの棚担当になりました。バイイングまで全部任せてもらったので、新人にしてはずいぶんいいポジションを与えてもらったように思いますね。仕事自体はとっても楽しかった。それこそ砂漠が水を吸収するように知識も得られたし、自分でもいろいろと工夫しました。結局、ABCには2年弱くらいいましたね。
六本木ヒルズができる前に“シンク・ゾーン”というスペースがあったんですが、そこに隣接して映像のコーナーとIDEE(イデー)のカフェが入り、そこにABCが建築やデザイン系の書籍を集めたコーナーを出すことになったんですが、その立ち上げもやらせてもらいました。それが終わった時に、なんとなく、自分の中でやり切ったかなと思うものがありましたね。
大学卒業後、このまま働きたくないなあと思って(笑)、日本橋郵便局のアルバイトで貯めたお金を握りしめてカナダに留学しました。余ったお金で“幅的お祭りを巡るツアー”というのを勝手に組み立てて、働く前に見ておきたいものを全部、ツール・ド・フランスとかジャズ・フェスティバルとかグッゲンハイム美術館とかアアルトのコエタロなどを、好き勝手にバックパックで見て回りました。
子どもの頃から本がずっと好きだったところに、大学で美術を勉強したことで、アートブックを作るのなんて面白そうだ、という感じで漠然と興味を持っていました。そして旅行から帰ってきて職業を選択しようという時には、何となく本に絡んだ仕事をしたいなと思っていました。小売りでも本を作る側でもよかったんです。
しかし当時は就職は超・氷河期。しかも、僕は就業経験もない。で、困っていたところに、偶然青山ブックセンター(以下ABC)の求人を見て、就業経験なしでも大丈夫ということで、受けたら採用されました。ただ倒産する直前で会社も最悪の状態ですし、コストもカットにカットを重ねているような、大変な状況でしたね。
入社後に配属されたのは六本木店で、建築とかデザインの棚担当になりました。バイイングまで全部任せてもらったので、新人にしてはずいぶんいいポジションを与えてもらったように思いますね。仕事自体はとっても楽しかった。それこそ砂漠が水を吸収するように知識も得られたし、自分でもいろいろと工夫しました。結局、ABCには2年弱くらいいましたね。
六本木ヒルズができる前に“シンク・ゾーン”というスペースがあったんですが、そこに隣接して映像のコーナーとIDEE(イデー)のカフェが入り、そこにABCが建築やデザイン系の書籍を集めたコーナーを出すことになったんですが、その立ち上げもやらせてもらいました。それが終わった時に、なんとなく、自分の中でやり切ったかなと思うものがありましたね。
エディター・石川次郎氏との出会い
実は、ABCにいたある日、お店によく来てくれていた『AXIS』の編集長の石橋さんという方に、「ちょっとウチで書いてみない?」と声をかけていただいたんです。それで、店にはナイショで文章を書く仕事もするようになりました。それがその後、いろいろ広がり、建築・デザインに関する記事をあちこちに書くようになっていったんです。
そんな時に出会ったのが石川次郎さんです。VALS(バルス)さんが作った『アイエヌ』というフリーペーパーに本を紹介する記事を書いていたんですが、ある時「素敵な翁について」というタイトルで北大路魯山人や花森安治などの本をピックアップして“素敵な翁=おじいちゃんとは何ぞや?”みたいな話を書きました。それをたまたま次郎さんが見て「こいつ面白いな」っていうことで会うことになったんです。
今でもよく覚えていますが、愛宕ヒルズのベトナム料理屋に呼び出されてご飯を食べて。旅が好きで世界を色々見て回った時の話などをしていたら、突然、「ウチに来たら?」ってスカウトされたんですよ。その場で給料まで提示されて、それがそれまで貰っていた給料の倍くらい。その場で「行きます!」って即答(笑)! ジェイ・アイに入社しました。
入社してからは、雑誌やカタログを作る仕事をしていたんですが、あるとき、六本木ヒルズに新しいTSUTAYAを作るというプロジェクトが立ち上がり、全体のプロデュースでジェイ・アイが関わることになたんです。
それまでのTSUTAYAは渋谷のスクランブル交差点のような通行量の多いような立地にあるイメージでしたし、洋書などは全く扱っていなかった。TSUTAYAとしては六本木ヒルズに入りたい、逆に森ビルさんからは従来のTSUTAYAとは全く違う店を作ってほしいというオーダーがありました。
森ビルさんから六本木ヒルズのコミッティー・メンバーだった石川さんにプロデュースの依頼があり、全て外部のプロデュースによる初のTSUTAYAを作るということになったんです。
ストア・アイデンティティやグラフィックまわりは佐藤可志和さん、内装は、当時LDK、後にカフェ・カンパニーを立ち上げられた入川(秀人)さん、MDの部分をジェイ・アイが担当するという分業でした。
僕は当時26歳だったんですけど、次郎さんから「お前六本木で本売ってただろ、よろしく」という感じで指名されて、1人で担当することになったんです。
約2万冊の本のバイイングを1人で担当。これは大変でしたね。六本木ヒルズにはいろいろ複雑な要素が絡み合っていて、それに合わせて従来とは全く異なるTSUTAYAブランドを作り上げましょう、という漠然としたコンセプトは決まっていたんですが、具体化しない。そこに、WEST WALK側に有隣堂さんの出店が決まってしまい、ふつうの書店が不要であることが明らかになってしまった。どうしよう? となったんです。
そんな時に出会ったのが石川次郎さんです。VALS(バルス)さんが作った『アイエヌ』というフリーペーパーに本を紹介する記事を書いていたんですが、ある時「素敵な翁について」というタイトルで北大路魯山人や花森安治などの本をピックアップして“素敵な翁=おじいちゃんとは何ぞや?”みたいな話を書きました。それをたまたま次郎さんが見て「こいつ面白いな」っていうことで会うことになったんです。
今でもよく覚えていますが、愛宕ヒルズのベトナム料理屋に呼び出されてご飯を食べて。旅が好きで世界を色々見て回った時の話などをしていたら、突然、「ウチに来たら?」ってスカウトされたんですよ。その場で給料まで提示されて、それがそれまで貰っていた給料の倍くらい。その場で「行きます!」って即答(笑)! ジェイ・アイに入社しました。
入社してからは、雑誌やカタログを作る仕事をしていたんですが、あるとき、六本木ヒルズに新しいTSUTAYAを作るというプロジェクトが立ち上がり、全体のプロデュースでジェイ・アイが関わることになたんです。
それまでのTSUTAYAは渋谷のスクランブル交差点のような通行量の多いような立地にあるイメージでしたし、洋書などは全く扱っていなかった。TSUTAYAとしては六本木ヒルズに入りたい、逆に森ビルさんからは従来のTSUTAYAとは全く違う店を作ってほしいというオーダーがありました。
森ビルさんから六本木ヒルズのコミッティー・メンバーだった石川さんにプロデュースの依頼があり、全て外部のプロデュースによる初のTSUTAYAを作るということになったんです。
ストア・アイデンティティやグラフィックまわりは佐藤可志和さん、内装は、当時LDK、後にカフェ・カンパニーを立ち上げられた入川(秀人)さん、MDの部分をジェイ・アイが担当するという分業でした。
僕は当時26歳だったんですけど、次郎さんから「お前六本木で本売ってただろ、よろしく」という感じで指名されて、1人で担当することになったんです。
約2万冊の本のバイイングを1人で担当。これは大変でしたね。六本木ヒルズにはいろいろ複雑な要素が絡み合っていて、それに合わせて従来とは全く異なるTSUTAYAブランドを作り上げましょう、という漠然としたコンセプトは決まっていたんですが、具体化しない。そこに、WEST WALK側に有隣堂さんの出店が決まってしまい、ふつうの書店が不要であることが明らかになってしまった。どうしよう? となったんです。
“楽しい違和感”がポイント
これは今でも僕が続けている方法論なんですが、クライアントが何をやりたくてこの場所に本屋を作ろうとしているのか、ということを知るために、まず関係者に徹底的にインタビューをするんですよ。最初にTSUTAYAさんの関係者から話を聞いたんですが、そこから出てきたのが“ライフスタイルの提案をしたい”ということでした。
そして“ライフスタイルって何?”と話をしているうちに出てきた要素が、「トラベル」「フード」「デザイン」「アート」という4つのジャンルです。だとしたら、その4つのジャンルを徹底的に揃えた本屋さんを作りましょう、ということで本を集めはじめたんです。今でもその4つのテーマ別のフダは今でも天井から下がっていますよ。
総合書店のような文芸を著者別にABC順で並べたり、文庫コーナーがあったり、という売り場構成は全くやらなかった。一方で夏目漱石とかも入れたいじゃないですか。僕はガルシア・マルケス大好きですから「『百年の孤独』が入ってない本屋なんて!」って思うんです(笑)。そこで、ある意味苦肉の策なのかもしれないんですが、ガルシア=マルケスなら「旅」の「南米」コーナーに置く、という本棚を編集してみた。
通常、文学のコーナーにあるような本が旅のコーナーにふとあって、たとえば『地球の歩き方 コロンビア』の隣にガルシア・マルケスの『百年の孤独』が並んでいる。お客さんの想像しないようなところに意外なものがある、という“楽しい違和感”が本の小売りとしては新しかったと思いますね。
当時はアマゾンが全盛。そんな時に、本の小売りが目指すべきものに図らずも出会ってしまった、という感じでしょうか。アマゾンのように本のタイトルや著者など決まっているものを検索するのではなくて、何かないかな?という感じで思ってもいなかったものに出くわす、そういう“幸福なアクシデント”みたいなものを誘発するのが幅流の本屋づくりなんです。
もちろんTSUTAYAさんからは最初は「分かりづらい」と言われました。TSUTAYAさんは真面目で常識的な棚づくりしかしてこなかった会社ですし、洋書も扱ったことがなかった。ディストリビューターの洋販を紹介して口座を作ることからのスタートでした。
しかも、期間が半年くらいしかなく、泣きそうなくらい厳しい日々でしたね。お店全体に影響が及ぶような大仕事はそれが初めてでしたしね。ただ、本のセレクトに関しては迷いはありませんでしたが。
本のセレクトはまず王道感というか、経年変化に耐えうるクラシックな本を柱として並べました。これは好評で、たとえば食のコーナーだったら『ティファニーのテーブルマナー』が食のコーナーの最初のベストセラーになったんです。北大路魯山人の『料理王国』なども売れましたね。それまでの読書体験に基づくセレクトです。六本木ヒルズという立地から、とにかく新しいものを、となりそうですが、そうではないものを差し込んで行きました。
そして“ライフスタイルって何?”と話をしているうちに出てきた要素が、「トラベル」「フード」「デザイン」「アート」という4つのジャンルです。だとしたら、その4つのジャンルを徹底的に揃えた本屋さんを作りましょう、ということで本を集めはじめたんです。今でもその4つのテーマ別のフダは今でも天井から下がっていますよ。
総合書店のような文芸を著者別にABC順で並べたり、文庫コーナーがあったり、という売り場構成は全くやらなかった。一方で夏目漱石とかも入れたいじゃないですか。僕はガルシア・マルケス大好きですから「『百年の孤独』が入ってない本屋なんて!」って思うんです(笑)。そこで、ある意味苦肉の策なのかもしれないんですが、ガルシア=マルケスなら「旅」の「南米」コーナーに置く、という本棚を編集してみた。
通常、文学のコーナーにあるような本が旅のコーナーにふとあって、たとえば『地球の歩き方 コロンビア』の隣にガルシア・マルケスの『百年の孤独』が並んでいる。お客さんの想像しないようなところに意外なものがある、という“楽しい違和感”が本の小売りとしては新しかったと思いますね。
当時はアマゾンが全盛。そんな時に、本の小売りが目指すべきものに図らずも出会ってしまった、という感じでしょうか。アマゾンのように本のタイトルや著者など決まっているものを検索するのではなくて、何かないかな?という感じで思ってもいなかったものに出くわす、そういう“幸福なアクシデント”みたいなものを誘発するのが幅流の本屋づくりなんです。
もちろんTSUTAYAさんからは最初は「分かりづらい」と言われました。TSUTAYAさんは真面目で常識的な棚づくりしかしてこなかった会社ですし、洋書も扱ったことがなかった。ディストリビューターの洋販を紹介して口座を作ることからのスタートでした。
しかも、期間が半年くらいしかなく、泣きそうなくらい厳しい日々でしたね。お店全体に影響が及ぶような大仕事はそれが初めてでしたしね。ただ、本のセレクトに関しては迷いはありませんでしたが。
本のセレクトはまず王道感というか、経年変化に耐えうるクラシックな本を柱として並べました。これは好評で、たとえば食のコーナーだったら『ティファニーのテーブルマナー』が食のコーナーの最初のベストセラーになったんです。北大路魯山人の『料理王国』なども売れましたね。それまでの読書体験に基づくセレクトです。六本木ヒルズという立地から、とにかく新しいものを、となりそうですが、そうではないものを差し込んで行きました。
座ってコーヒーが飲める本屋さん
スターバックスを入れたのも大正解でした。駅前の大型書店などではお客さんは立ち読みもあまりできないですが、なるべく多くの本と出会ってもらうために、滞留時間を長くしよう。そのためには、ソファを置こうということになったんです。石川さんも、アメリカで見てきた「バーンズ・アンド・ノーブル」のような書店がなぜ日本にないんだ、と不満を持たれていたんです。
六本木店ができる前年にも、すでにTSUTAYAとスタバの複合店舗が、例えば北千住のルミネにあったんですが、“この線から向こうにはコーヒーを持っていってはダメですライン”みたいなのがあったので、そんなことはやめて、店内はどこにでもコーヒーを持っていってよし、ということにしましょう。ソファに座れて、コーヒーが飲めて、本を選べるという本屋にしましょう、という方針が決まったのです。
そこから石川と2人でTSUTAYAさんを大説得です。椅子を置けるスペースがあるなら商品を置いて回転率を上げるのが当たり前、という能率至上主義の企業に“非能率の能率”みたいなものをどうやって認めてもらうか。この説得作業はとても勉強になりました。現在でも仕事上そういう“非能率の能率”を説得するというシーンは多々ありますからね。
もちろん、効率主義の考え方も理解はできるんですが、本というものを扱う以上、能率100%で考えると本質からズレていってしまうんです。長い目で見ると非効率の部分によって全体がうまく回る部分もあるはずだ、と当時TSUTAYAストアの社長でいらした木村元昭さん(TSUTAYA HOLDINGS取締役:09年1月現在)と何度も打ち合わせを重ねて、最終的にはプランを認めていただいたんです。
今でも六本木のお店はTSUTAYAさんの中でも相当異質な存在です。他の直営店を見ても、似たようなお店を出されていますが、やはり違うものになっていますよね。ジェイアイが関わったのは結局TSUTAYA TOKYO ROPPONGIだけですが、やはりあの時(2003年)の土地の空気感とか、時代の流れがあったからこそ成り立ったんでしょうね。
六本木店ができる前年にも、すでにTSUTAYAとスタバの複合店舗が、例えば北千住のルミネにあったんですが、“この線から向こうにはコーヒーを持っていってはダメですライン”みたいなのがあったので、そんなことはやめて、店内はどこにでもコーヒーを持っていってよし、ということにしましょう。ソファに座れて、コーヒーが飲めて、本を選べるという本屋にしましょう、という方針が決まったのです。
そこから石川と2人でTSUTAYAさんを大説得です。椅子を置けるスペースがあるなら商品を置いて回転率を上げるのが当たり前、という能率至上主義の企業に“非能率の能率”みたいなものをどうやって認めてもらうか。この説得作業はとても勉強になりました。現在でも仕事上そういう“非能率の能率”を説得するというシーンは多々ありますからね。
もちろん、効率主義の考え方も理解はできるんですが、本というものを扱う以上、能率100%で考えると本質からズレていってしまうんです。長い目で見ると非効率の部分によって全体がうまく回る部分もあるはずだ、と当時TSUTAYAストアの社長でいらした木村元昭さん(TSUTAYA HOLDINGS取締役:09年1月現在)と何度も打ち合わせを重ねて、最終的にはプランを認めていただいたんです。
今でも六本木のお店はTSUTAYAさんの中でも相当異質な存在です。他の直営店を見ても、似たようなお店を出されていますが、やはり違うものになっていますよね。ジェイアイが関わったのは結局TSUTAYA TOKYO ROPPONGIだけですが、やはりあの時(2003年)の土地の空気感とか、時代の流れがあったからこそ成り立ったんでしょうね。
独立、BACH設立
TSUTAYA TOKYO ROPPONGIが話題になって、そこから“BOOK246”でカフェに併設するブックショップの仕事につながりました。そのBOOK246を『BRUTUS』の表紙で紹介していただき、「本が仕事になるかもしれないな」と思いはじめたころに手がけた仕事が三陽商会の“LOVELESS”です。
ファッションのセレクトショップですが、そこに自分たちの文化とかアイデンティティを表現していくうえで本は必要なツールなんだ、という吉井雄一さんのオファーがあって、本のMDとして参加させていただいたんです。それがその後インテリアショップの“CIBONE”などにも広がって、色々なところに本が入り込んでいくお手伝をするようになりました。
こうして本は面白いですよ、ということを本屋をやらずにアナウンスしていく、というやり方はアリだな、と思えるようになりました。BACHの設立は2005年ですが、いつの間にか独立して職業になっていた、というのが正直なところです(笑)
この「Shibuya Publishing Booksellers(シブヤ・パブリッシング・ブックセラー)」は、出版社があってその隣に本屋があるという構成で、出版社で打ち合わせたものが本になってそのまま隣にある本屋の平台に並びます。この本を作る場所と売る場所をつなげるというアイデアは、オーナーの福井さんと最初に話し合った時に出てきました。
ここではオリジナルのクロックスを売ったり、オリジナルの写真集を作ったりもしています。浅野忠信さんの写真集を1冊1000円で販売しましたが、客層もあってかなり売れるんです。そういう着実に売れるものを作ることで、売上や集客の下支えになっています。書店流通の掛け率が変らないんだったら、別の部分でそういう工夫をしていくことが必要で、そこで大切なのはやはりオリジナルなものを作るということです。
国立新美術館(2007年)では本のMDを行いました。やはりあそこでないと買えないオリジナルMDを作りました。どうやって“オリジナル力”のあるものを作れるかと考えて、佐藤可志和さんが美術館のロゴなどを含めた全体のCIを担当されていたので、そのロゴを使うではなく、一つ一つを可志和さんにデザインしてもらいました。そうするといいものを作ることができて、これはやはり売れるんです。
単純に本は面白い/それを多くの人に伝えたい/でも本屋をやるのは辛い/でも絶対本に対する潜在的なニーズはある、といろいろ四苦八苦しているうちに、いろんな所からお声がかかるようになって、あらゆるところに本棚を作ることが仕事になり、現在に至っています。
ファッションのセレクトショップですが、そこに自分たちの文化とかアイデンティティを表現していくうえで本は必要なツールなんだ、という吉井雄一さんのオファーがあって、本のMDとして参加させていただいたんです。それがその後インテリアショップの“CIBONE”などにも広がって、色々なところに本が入り込んでいくお手伝をするようになりました。
こうして本は面白いですよ、ということを本屋をやらずにアナウンスしていく、というやり方はアリだな、と思えるようになりました。BACHの設立は2005年ですが、いつの間にか独立して職業になっていた、というのが正直なところです(笑)
この「Shibuya Publishing Booksellers(シブヤ・パブリッシング・ブックセラー)」は、出版社があってその隣に本屋があるという構成で、出版社で打ち合わせたものが本になってそのまま隣にある本屋の平台に並びます。この本を作る場所と売る場所をつなげるというアイデアは、オーナーの福井さんと最初に話し合った時に出てきました。
ここではオリジナルのクロックスを売ったり、オリジナルの写真集を作ったりもしています。浅野忠信さんの写真集を1冊1000円で販売しましたが、客層もあってかなり売れるんです。そういう着実に売れるものを作ることで、売上や集客の下支えになっています。書店流通の掛け率が変らないんだったら、別の部分でそういう工夫をしていくことが必要で、そこで大切なのはやはりオリジナルなものを作るということです。
国立新美術館(2007年)では本のMDを行いました。やはりあそこでないと買えないオリジナルMDを作りました。どうやって“オリジナル力”のあるものを作れるかと考えて、佐藤可志和さんが美術館のロゴなどを含めた全体のCIを担当されていたので、そのロゴを使うではなく、一つ一つを可志和さんにデザインしてもらいました。そうするといいものを作ることができて、これはやはり売れるんです。
単純に本は面白い/それを多くの人に伝えたい/でも本屋をやるのは辛い/でも絶対本に対する潜在的なニーズはある、といろいろ四苦八苦しているうちに、いろんな所からお声がかかるようになって、あらゆるところに本棚を作ることが仕事になり、現在に至っています。
“異物混入”がカギ
これまで本の文化を作ってきた本屋業界に対するリスペクトはもちろんありますが、その中だけではすでに限界を感じます。むしろ異物が混入することでミックスアップされる方が面白い。たとえば洋服屋さんやカフェ、百貨店などそれぞれのやり方とか譲れないものがそれぞれあって、そういうものとぶつかりながら、そういう中で、どうしたら本がそこの場所に似つかわしいものとして置かれていくのかを考えるのが好きなんです。
本屋さんに興味を持っていない、本屋になんて行かないような人たちに、いかに本を手に取ってもらうかを、ストレスや制約がある中で考える方が面白いですね。洋服屋さんでも家具屋さんでもいいから、そういうショップに来たお客さんがふと本を手に取ってパラパラっとページをめくってくれる瞬間が嬉しいんです。
例えばLOVELESSも熱狂的な人気があって、開店前に行列ができるような状態だったんですが、そこに集まるお客さんはLOVELESSというブランドに恋をしていて、ショップがお薦めするものだったら何でも買っちゃう、みたいな状態だったんです。それで、本もよく売れたんですよ。
あれは本が欲しかったというよりも、“LOVELESSと一体化したい欲”みたいなものだったんではないかと思うんですよ。買うことによって自分のショップに対する親和性がより高まっていくという感じ。そういう“LOVELESSがお薦めする本だから面白いのかも”というルートでもいいから、いい本との出会いを作っていきたい。
本の業界にはアカデミックなプライドみたいなものがあるじゃないですか。洋服屋さんのおまけみたいなものとして買われるのはイヤだ、みたいな。でも僕はモテたくて、みたいな動機でもなんでもいいから、本を手に取らせなくてはダメだと思うんです。
本全体のブランディングというと大げさかもしれませんが、本というものも面白くてなかなかチャーミングな奴ですよー、ということをいろんな層に伝えていかないとこれからはキツいと思いますし、どんどんニッチなものになってしまう。いろいろな本の楽しみ方があっていいし、もっと本の多様性が伝わってほしいですね。
ネットでの情報とは違って、本はそれぞれの責任の所在が明確じゃないですか。それなのに多様性があって、やっぱり面白いメディアだなと改めて思います。ただ、その面白さは遅効性なんですよ。それを判ってもらうためには習慣として読み続けていただく風景を作らなくてはいけない。まずは本を手に取るという行為自体を、今まで2週間に1回だったものを毎週してもらえるようにしたい。
ネット上では1次情報が駆け巡っていますけど、本はそれを集めて、編んで、選ばれた情報を方向付けしてまとめられた2次情報の集積として面白いメディアなんです。たくさんの人に瞬間で何かを伝える、ということには向いていませんが、逆に心の襞にピンポイントで何かをプスッと刺していく、ということに関しては、本はまだまだ果たすべき役目があると思います。
本屋さんに興味を持っていない、本屋になんて行かないような人たちに、いかに本を手に取ってもらうかを、ストレスや制約がある中で考える方が面白いですね。洋服屋さんでも家具屋さんでもいいから、そういうショップに来たお客さんがふと本を手に取ってパラパラっとページをめくってくれる瞬間が嬉しいんです。
例えばLOVELESSも熱狂的な人気があって、開店前に行列ができるような状態だったんですが、そこに集まるお客さんはLOVELESSというブランドに恋をしていて、ショップがお薦めするものだったら何でも買っちゃう、みたいな状態だったんです。それで、本もよく売れたんですよ。
あれは本が欲しかったというよりも、“LOVELESSと一体化したい欲”みたいなものだったんではないかと思うんですよ。買うことによって自分のショップに対する親和性がより高まっていくという感じ。そういう“LOVELESSがお薦めする本だから面白いのかも”というルートでもいいから、いい本との出会いを作っていきたい。
本の業界にはアカデミックなプライドみたいなものがあるじゃないですか。洋服屋さんのおまけみたいなものとして買われるのはイヤだ、みたいな。でも僕はモテたくて、みたいな動機でもなんでもいいから、本を手に取らせなくてはダメだと思うんです。
本全体のブランディングというと大げさかもしれませんが、本というものも面白くてなかなかチャーミングな奴ですよー、ということをいろんな層に伝えていかないとこれからはキツいと思いますし、どんどんニッチなものになってしまう。いろいろな本の楽しみ方があっていいし、もっと本の多様性が伝わってほしいですね。
ネットでの情報とは違って、本はそれぞれの責任の所在が明確じゃないですか。それなのに多様性があって、やっぱり面白いメディアだなと改めて思います。ただ、その面白さは遅効性なんですよ。それを判ってもらうためには習慣として読み続けていただく風景を作らなくてはいけない。まずは本を手に取るという行為自体を、今まで2週間に1回だったものを毎週してもらえるようにしたい。
ネット上では1次情報が駆け巡っていますけど、本はそれを集めて、編んで、選ばれた情報を方向付けしてまとめられた2次情報の集積として面白いメディアなんです。たくさんの人に瞬間で何かを伝える、ということには向いていませんが、逆に心の襞にピンポイントで何かをプスッと刺していく、ということに関しては、本はまだまだ果たすべき役目があると思います。
小売店としての書店に欠けているもの
僕がやりたいのは、“よい本と出会える環境を整えたい”ということなのですが、本屋さんが必ずしもそういう場所ではなくなっている現状もあります。
売れる本の数は少なくなっているのに、出ている本のタイトル数はどんどん増えている。出版社としては、とりあえず取次に入れればお金は入ってくるから、今月必ず5冊出さなきゃ、10冊出さなきゃ、みたいな感じで本を出すようになってしまい、返本率が30%でも70%でも構わない、という状況に。
で、結局、そういうものの中にいい本が埋もれてしまっているんです。ただでさえ本というツール自体の存在価値や立ち位置をうまく整理していかなければいけない時期なのに、それが分かり辛くなっている。
僕は本という面白いメディアを伝える本屋さんというスペースの中で何ができるのか、ということを考えたい。クライアントのオーダーや店の大小など場所はさまざまですけど、人と本の出会う場所としての本屋をちゃんとやり直したい、というかリセットしたいんです。
日本で本屋が少なくなってしまったのは、単純に書籍流通の問題ばかりとは言い切れないと思います。今潰れていってる駅前書店には、小売りの意識のあるところが少ないと思うんです。小売店がお客さんのニーズを見極めようとする努力とか、お客さんの潜在的なところに何が潜んでいるのか、ということをちゃんと把握して、それに対するサービスを提供しようとする努力を日々重ね上げて行っている書店は少ないと思いますね。
自分たちの売りたい物を選ぶのではなく、取次のパターン配分で来たものをそのまま売って、余ったものは返品。それだけみたいなお店が多いんです。小売りの人々がやっている努力とかアイデアが今の書店には足りないような気がしますね。
例えば本屋なら、自発的にそれを選び、本当にそれを面白いと思って売っているのか。雑誌であればそれを編集者が本当に載せようと思って掲載しているのか、それとも載せさせられているのか。実は読み手の側はかなり分かってしまっているんですよ。その辺の嗅覚は今の消費者はかなり敏感ですから、お店や誌面から伝わってしまう。本を巡るシステム全体に問題があるのは確かですが、それをかいくぐってオリジナルなものを考えて行かないと面白いことはできないと思いますね。
例えば大型書店を考えてみると、本はあるんだけど多すぎる。僕も好きでよく使うから分かるんですが、確かに探せば求める本はちゃんと見つかりますが、そこに至るまでが大変。回遊して楽しい、という量ではないんです。椅子のあるお店なんてまだまだ少ないですし。ライブラリー的に、“探しているものがすぐ出てくる”ことと、回遊して知らない本に出くわす“回遊していて楽しい”ことの2つがあれば、もっと大手の書店も面白くなってくるはずです。
「この本を売ってやろう」という売り手や作り手の意志は、本屋の棚にも宿りますよね。例えばこの間ベルリンに行った時も、ネットとかには展開していない老舗のブックショップがあったんですが、とにかく大感動。そこに行って5時間過ごしました(笑)。海外だと知らない出版社も多いし、知らない本ばかりですが、なんとなく店を見ていると良さそうな本というのは匂い立ってくるんです。
村上春樹が「紀ノ国屋の野菜はよく調教されている」みたいことを『ダンスダンスダンス』で書いていましたが、何かそういう売り手の意志を店の努力で本棚に宿らせることはできると思います。数字的な部分にマネジメントして関わっていく部分の一方で、言葉に説明できない“熱情”みたいなものを上手く組み合わせてやっていくことが必要だと思いますね。
まだ既存の本屋さんとは仕事をしたことはありません。今はあえて自分の仕事の段階として、小さくてセレクトされたお店の仕事をしていますが、いずれそういうところにも取り組んでいきたいですね。大きくなり過ぎてしまった郊外の大型書店などはたくさんありますし、やれることはまだまだあります。
売れる本の数は少なくなっているのに、出ている本のタイトル数はどんどん増えている。出版社としては、とりあえず取次に入れればお金は入ってくるから、今月必ず5冊出さなきゃ、10冊出さなきゃ、みたいな感じで本を出すようになってしまい、返本率が30%でも70%でも構わない、という状況に。
で、結局、そういうものの中にいい本が埋もれてしまっているんです。ただでさえ本というツール自体の存在価値や立ち位置をうまく整理していかなければいけない時期なのに、それが分かり辛くなっている。
僕は本という面白いメディアを伝える本屋さんというスペースの中で何ができるのか、ということを考えたい。クライアントのオーダーや店の大小など場所はさまざまですけど、人と本の出会う場所としての本屋をちゃんとやり直したい、というかリセットしたいんです。
日本で本屋が少なくなってしまったのは、単純に書籍流通の問題ばかりとは言い切れないと思います。今潰れていってる駅前書店には、小売りの意識のあるところが少ないと思うんです。小売店がお客さんのニーズを見極めようとする努力とか、お客さんの潜在的なところに何が潜んでいるのか、ということをちゃんと把握して、それに対するサービスを提供しようとする努力を日々重ね上げて行っている書店は少ないと思いますね。
自分たちの売りたい物を選ぶのではなく、取次のパターン配分で来たものをそのまま売って、余ったものは返品。それだけみたいなお店が多いんです。小売りの人々がやっている努力とかアイデアが今の書店には足りないような気がしますね。
例えば本屋なら、自発的にそれを選び、本当にそれを面白いと思って売っているのか。雑誌であればそれを編集者が本当に載せようと思って掲載しているのか、それとも載せさせられているのか。実は読み手の側はかなり分かってしまっているんですよ。その辺の嗅覚は今の消費者はかなり敏感ですから、お店や誌面から伝わってしまう。本を巡るシステム全体に問題があるのは確かですが、それをかいくぐってオリジナルなものを考えて行かないと面白いことはできないと思いますね。
例えば大型書店を考えてみると、本はあるんだけど多すぎる。僕も好きでよく使うから分かるんですが、確かに探せば求める本はちゃんと見つかりますが、そこに至るまでが大変。回遊して楽しい、という量ではないんです。椅子のあるお店なんてまだまだ少ないですし。ライブラリー的に、“探しているものがすぐ出てくる”ことと、回遊して知らない本に出くわす“回遊していて楽しい”ことの2つがあれば、もっと大手の書店も面白くなってくるはずです。
「この本を売ってやろう」という売り手や作り手の意志は、本屋の棚にも宿りますよね。例えばこの間ベルリンに行った時も、ネットとかには展開していない老舗のブックショップがあったんですが、とにかく大感動。そこに行って5時間過ごしました(笑)。海外だと知らない出版社も多いし、知らない本ばかりですが、なんとなく店を見ていると良さそうな本というのは匂い立ってくるんです。
村上春樹が「紀ノ国屋の野菜はよく調教されている」みたいことを『ダンスダンスダンス』で書いていましたが、何かそういう売り手の意志を店の努力で本棚に宿らせることはできると思います。数字的な部分にマネジメントして関わっていく部分の一方で、言葉に説明できない“熱情”みたいなものを上手く組み合わせてやっていくことが必要だと思いますね。
まだ既存の本屋さんとは仕事をしたことはありません。今はあえて自分の仕事の段階として、小さくてセレクトされたお店の仕事をしていますが、いずれそういうところにも取り組んでいきたいですね。大きくなり過ぎてしまった郊外の大型書店などはたくさんありますし、やれることはまだまだあります。
本屋だからこそできる情報コンサルティング
これは青山ブックセンターにいた時に役に立ったんですが、本屋という場所は、世の中で何が売れていて何が実は売れていないかということが間近に分かるんです。本屋さんだから得られる情報、動いている世の中全般の流れみたいなものを敏感に感じることができるんです。本屋の現場では、売り場の商品としては20数パーセントの粗利しかないわけですけど、そこで蓄積された情報やアイデアの方が、僕はもっと価値があり、高く売れるものじゃないかと思うんです。本屋に集まってくる情報をいかに提示して売っていくのか、ということを、特に大手の書店は考えるべき時に来ていると思いますね。
例えば本屋さんだからこそ分かる生の声とかアイデアをパッケージして商品にすることもできるんじゃないかと思うんです。要は本屋さんがもう少しよろず屋になっていくべきでは。専門として本だけを売るのではなくね。現にうち自身も本を売るのではなくアイデアを売る会社としてやってるわけですから。
例えば「NIKEのDUNKに関する来歴が分かる本を100冊選ぶ」という広告の仕事があったんですが、そういう話がうちだけではなくて大手の書店にも行くようであってほしいですね。
洋服屋や家具屋とか、いろんなところが工夫しているような、お客さんが回遊して、商品に引っ掛かるような仕掛けづくりは、本屋でも重要です。たとえば洋服だったら、フィッティングの時に「実はこういう珍しい生地を使っているんですよ」なんて素材の話なんかをされるとつい欲しくなったりするでしょ。洋服なら、量販店を別にすれば、そういうサジェスチョンとかその背景にある物語なくして買えないわけです。嗜好品として考えると、そこに潜んでいる物語がすごく重要で、本というものが今、もっともっと嗜好品という方向に舵を切らざるを得ないと思いますね。
例えば本屋さんだからこそ分かる生の声とかアイデアをパッケージして商品にすることもできるんじゃないかと思うんです。要は本屋さんがもう少しよろず屋になっていくべきでは。専門として本だけを売るのではなくね。現にうち自身も本を売るのではなくアイデアを売る会社としてやってるわけですから。
例えば「NIKEのDUNKに関する来歴が分かる本を100冊選ぶ」という広告の仕事があったんですが、そういう話がうちだけではなくて大手の書店にも行くようであってほしいですね。
洋服屋や家具屋とか、いろんなところが工夫しているような、お客さんが回遊して、商品に引っ掛かるような仕掛けづくりは、本屋でも重要です。たとえば洋服だったら、フィッティングの時に「実はこういう珍しい生地を使っているんですよ」なんて素材の話なんかをされるとつい欲しくなったりするでしょ。洋服なら、量販店を別にすれば、そういうサジェスチョンとかその背景にある物語なくして買えないわけです。嗜好品として考えると、そこに潜んでいる物語がすごく重要で、本というものが今、もっともっと嗜好品という方向に舵を切らざるを得ないと思いますね。
“容赦のない場所”に本を届ける楽しさ
要は他人好きというか、自分ひとりで凝り固まったアイディアできる範囲は狭いですし、自分を違う次元に連れて行ってくれるのは外からのアイデアだったり感情だったり、他者とのかかわりにこそあると思っているんです。
例えば面白い本を1日部屋に閉じこもって4冊読むよりは、2冊を読んで、その2冊で面白かった話を携えて、その2冊分の時間を他人と会って飲んだ方がいい。そちらの人生の方を僕は推奨しますね(笑)。
本を読むことが目的なのではなくて、本を読んで得た情報をもとに、いかに面白おかしい人生を歩むかを考え、暮らしに転化していくかということが大切だと思うんです。脳梗塞の人たち向けの教材も同じ。たとえば手が動くことが目的ではなくて、動いた手で何を掴むのか、本人が何をするのか、の方が重要だと思うんです。
他人と親和するのかぶつかり合うのか、どちらにしても他人と関わってこそ何かができる、という考え方はずっと変わらないと思いますね。だからこそ僕は自分で本屋さんを持たずに、状況に応じて、でもやっぱり自分のノウハウや好みも絡めながら、いろんな形の本屋さんを作っていくというスタイルで仕事をしているんだと思いますね。
たとえば「ユトレヒト」とか「ハックネット」のように、本屋さんをやりつつ他のお店のプロデュースもしている、という本屋さんもありますが、どうしてもオーダーする側は “ユトレヒト風味”“ハックネット風”のようなものを求めてくると思うんです。
僕の場合は、与えられた場所の状況や環境に応じて最も似つかわしい本を、どういう風に並べて読んでもらうか、ということを、スピード感を持って勝負したいですね。
愛知県立芸術大学の非常勤講師をしているので、学生と話すことがあるんですが、彼らは「グーグルを検索して出てこないものは世の中に存在しないということと同義だ」なんて平気で言いますからね。そういう方向に意識のあり方がシフトしているなかで、本の目利きとして何を提案していくのか。そういう若年層に対してこそ、むしろ可能性があるんじゃないかと思うんです。
ネットで検索することの一方で、じわじわいい感じで効いてくる遅効性のメディアである本の面白さを伝えることは、これからもっと大切になってくると思います。“自分への投資感”みたいなものにも、これからもっとお金が落ちるようになるでしょうね。
今の学生たちに対するアプローチについてはこれから根本的に考えないといけない時期にきていると思います。彼らに対しては、今まで僕がやってきたノウハウとは違ったやり方を考えないと届かないのかなという感じもしています。
これもまたさっきの脳梗塞のリハビリと同じように“容赦のない場所”。ニーズを捉えるために、話をじっくり聞いて、そこに何が似つかわしいのかを考えていく。やっぱりこういうアプローチが僕は好きなんでしょうね。
[インタビュー/文:本橋康治+『ACROSS』編集部]
例えば面白い本を1日部屋に閉じこもって4冊読むよりは、2冊を読んで、その2冊で面白かった話を携えて、その2冊分の時間を他人と会って飲んだ方がいい。そちらの人生の方を僕は推奨しますね(笑)。
本を読むことが目的なのではなくて、本を読んで得た情報をもとに、いかに面白おかしい人生を歩むかを考え、暮らしに転化していくかということが大切だと思うんです。脳梗塞の人たち向けの教材も同じ。たとえば手が動くことが目的ではなくて、動いた手で何を掴むのか、本人が何をするのか、の方が重要だと思うんです。
他人と親和するのかぶつかり合うのか、どちらにしても他人と関わってこそ何かができる、という考え方はずっと変わらないと思いますね。だからこそ僕は自分で本屋さんを持たずに、状況に応じて、でもやっぱり自分のノウハウや好みも絡めながら、いろんな形の本屋さんを作っていくというスタイルで仕事をしているんだと思いますね。
たとえば「ユトレヒト」とか「ハックネット」のように、本屋さんをやりつつ他のお店のプロデュースもしている、という本屋さんもありますが、どうしてもオーダーする側は “ユトレヒト風味”“ハックネット風”のようなものを求めてくると思うんです。
僕の場合は、与えられた場所の状況や環境に応じて最も似つかわしい本を、どういう風に並べて読んでもらうか、ということを、スピード感を持って勝負したいですね。
愛知県立芸術大学の非常勤講師をしているので、学生と話すことがあるんですが、彼らは「グーグルを検索して出てこないものは世の中に存在しないということと同義だ」なんて平気で言いますからね。そういう方向に意識のあり方がシフトしているなかで、本の目利きとして何を提案していくのか。そういう若年層に対してこそ、むしろ可能性があるんじゃないかと思うんです。
ネットで検索することの一方で、じわじわいい感じで効いてくる遅効性のメディアである本の面白さを伝えることは、これからもっと大切になってくると思います。“自分への投資感”みたいなものにも、これからもっとお金が落ちるようになるでしょうね。
今の学生たちに対するアプローチについてはこれから根本的に考えないといけない時期にきていると思います。彼らに対しては、今まで僕がやってきたノウハウとは違ったやり方を考えないと届かないのかなという感じもしています。
これもまたさっきの脳梗塞のリハビリと同じように“容赦のない場所”。ニーズを捉えるために、話をじっくり聞いて、そこに何が似つかわしいのかを考えていく。やっぱりこういうアプローチが僕は好きなんでしょうね。
[インタビュー/文:本橋康治+『ACROSS』編集部]