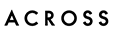Christian Wijnants(2007SS)
『here and there』vol.6/Nieves
編集会議で企画を通せたり、撮影や執筆、レイアウトとかをやらせてもらえるようになったのは10年くらい経ってからかな。編集会議では、自分が見つけてきた情報や企画を提案する。そこから誌面に吸い上げられることは滅多にありませんでしたが、いつも考える、ということをさせられたように思います。
ファッションについては1992年末、入社4年目ぐらいから下働きの下働きでパリコレに連れてってもらって、以来7-8年間続けて見ていました。パリコレの取材って、ものすごく過酷で、インビテーションの依頼にはじまり、電話してアポ取ったリ事前にそれが届いているかどうか全部チェックしたり、行く前から始まってるんです。現地入りしてからは、毎晩10時ぐらいまでご飯も食べないで駆け回ってました。会場が離れてますからね。
東京にいるとわからないんですけど、ファッションの世界では、パリっていう中心地が確実にあって、それに対してどういうスタンスを取るかっていうことが自分の立ち位置を決めることになるんです。
私は媒体内でも2枚目とか3枚目でパリコレを申し込む立場にいたので、とにかくチケットがもらえない。でも、『花椿』の中でパリコレのレポートを書かなくちゃいけないから、本当に見なきゃいけないのに。たぶん同じように苦労してる人は多いと思いますね。
たとえば、電話をかけてチケットくれくれって言うのはもちろんのこと、現場でインビテーション届かなかったけど入れろって強力にアピールして無理矢理入っちゃったり、チケットのような紙を持ってスッと入っちゃったりとか。とにかくみんないろんなことやってましたね。私もそういうど真ん中にいて、先輩方に囲まれながら見るための戦いをしなくちゃいけなかったんですけど、その戦いはその場で終わっちゃってる。入れたらああよかったで終わり。ところが、会場に入ってみると、日本人の席なんて末席もいいところ。新人のデザイナーにしろベテランのデザイナーにしろ、そういう人たちがやっていけてるのは日本という消費者がバックに控えているからであることは事実なのに、ショーに行ってみるとフロントロウは欧米人が占めている。そんな状況に甘んじてるのは何なんだろうって私なりに考えてみたら、その場だけの戦いをし続けてるからなんじゃないかっていう結論に至ったんです。
たぶん、日本人はパリコレにおける扱いの悪さを怒ってるんですけど、怒らせる原因は何かっていうと、日本っていう国がのっぺらぼうで怖いっていうか、どことなく正体不明な感じがするんじゃないかと思うんです。
そこで、私は、自分が『花椿』でレポートした文章を英語に訳して、こういう風に報道したので次はチケットくださいってやったんです。プレスルームに送ってもぱっと捨てられちゃったりするから、住所突き止めたりしてデザイナーに直接送ったりもしましたね。上司にもチケットの入手が難しいのはそういう理由です、と説得して翻訳の経費をもらって毎回、毎回送り続けました。
だからヴィクター&ロルフとかは、今でも私の顔を憶えててくれていて、いつだったかたまたま会ったときに、私はフリーになったからショーのチケットはもらえないよって言ったら、君は日本人でいちばん最初に自分のことをちゃんと書いてくれてそれを英語にしてちゃんと見せてくれたジャーナリストなのにねって言ってくれたりして。手間をかけてやってきて良かったなと思いましたね。
やっぱり地続きのヨーロッパの国々とは違う、日本っていう遠く離れた島国だからこそ、そこでもこのように報道しているっていうことを丁寧に伝えるべきかなっていう思いもありました。パリコレ主導のモードの世界は、欧米人の骨格に合うような美しい服を出していて、日本人のフラットなボディには似合うものではないし、歴史的に見てもまったく違うもの。パリコレについては、いろんな意味でそこにぶつかりながら学びましたけど、かなり厳しい世界であるのは事実。なかなか入り込めない世界なんですよ。
でも、同じようにパリのモード界に居ながらも違和感を感じて、違ったニュアンス、スタンスで作品を発表していきたいと思っているファッションデザイナーもいるんです。雑誌の編集者にもそういう人がいる。そんな「はみ出した者同士」っていうことで友だちができていった。実は、それが今の『here and there』のスタッフに繋がってきてるんです。そのなかのひとりが、今の『purple journal』の編集長のエレン・フライスです。