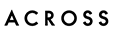春に向かって、ファッション/アパレル業界だけでなく、ライフスタイル・雑貨など、都内各所で様々な合同展示会が開催されている。そのなかで今回注目したのは、日本各地の作り手が集まる「大日本市」。企画しているのは2016年に創業300周年を迎えた株式会社中川政七商店だ。
毎回約2,000人が来場するという本イベントは2018年にスタート。2月と8月の年2回開催され、今回が3回目となり、45ブランドが参加した。元々2011年にスタートした「大日本市」は、中川政七商店が経営コンサルティングでお手伝いしたメーカーに出展を限定していた。しかし2018年2月に“開国宣言”をし、一般企業からも出展を募集。工芸メーカーの自立と成長の促進を目指した合同展示会となっている。会場となる天王洲アイルのB&C HALLには、地域ごとに色分けされた旗が上がり、活気にあふれていた。

出入口側に設置された投票コーナー。来場者がお気に入りの出展者のところにシールを貼って投票する。
「大日本市」の特徴は、出展者がすぐに手応えを感じられるところだという。
各ブースにはバーコードが設置され、来場者はそこですぐに受注が可能。その場で売上が計上されていくため、名刺を交換して終わりではない、すぐにビジネスに繋がる仕組みが用意されている。また、各出展者は1日ごとに目標を設定し、その達成率は全出展者で共有され順位が発表される。あわせて来場者がお気に入りの出展者にシールを貼って投票する公開アンケートも実施されていた。
「出展者のモチベーションアップに繋げたい」と中川政七商店の広報担当の佐藤菜摘さんは話す。
各ブースにはバーコードが設置され、来場者はそこですぐに受注が可能。その場で売上が計上されていくため、名刺を交換して終わりではない、すぐにビジネスに繋がる仕組みが用意されている。また、各出展者は1日ごとに目標を設定し、その達成率は全出展者で共有され順位が発表される。あわせて来場者がお気に入りの出展者にシールを貼って投票する公開アンケートも実施されていた。
「出展者のモチベーションアップに繋げたい」と中川政七商店の広報担当の佐藤菜摘さんは話す。
会場に入り最初に目に留まったのは、手漉き和紙の「名尾手すき和紙」だ。adidasのスニーカーの空箱や漫画や植物が混じったモダンな和紙が展示されており、なにより気になったのは、うっすらとTシャツが透けて見える大きな和紙。一体どうやって作られたのだろうか。

靴の空箱を使ったもの、お茶屋さんのために作ったお茶を混ぜたものなど、思わず触りたくなるような作品が並ぶ。
そんな斬新なデザインとアイディアの発案者は谷口弦さん。元禄時代から300年以上続く「名尾手すき和紙」の7代目だという。佐賀県の名尾は昔から和紙の里として知られ、最盛時は100軒以上の工房が軒を連ねていた。しかし、現在は谷口さんの工房1軒のみに。
2014年に島根県の「石州半紙」など3つの和紙がユネスコの無形文化遺産に登録されたが、「自分たちがこうして今作っている和紙が遺産と呼ばれるなんて」と谷口さんは違和感を感じ一念発起したのだそうだ。

植物や見慣れた漫画を使った和紙も。素材を分かるようにあえて粗めに裁断されているため、印象に残る一枚に。
谷口さんはもともと服好きで、某セレクトショップの販売スタッフとして福岡で働いていた時に、大量に余った靴の空箱やショッパーを目にし、これを何かに使えないだろうかとずっと考えていたのだそうだ。
地元に戻り、和紙のブランド「PAPER VALLEY」を立ち上げた谷口さんは、伝統的な手法だけでなく、新しい取り組みにも積極的にチャレンジ。そのひとつが、まだ立ち上げたばかりのブランド「KAMINARI PAPERWORKS ™️」だ。
通常、和紙の原料は梶や楮100%。なにかを混入させることは和紙という概念が崩れてしまうため良くないとされていたが、谷口さんはあえて違う素材を加えて新しいものを作った。

制作段階でゴミとなってしまうカカオの殻がパッケージに生まれ変わる!思わず香りを嗅いでしまいたくなる。
例えば広島県・尾道の「USHIO CHOCOLATL」で販売されるチョコレートのパッケージには、捨てられることになったカカオの殻が入っている。また、現在進んでいるプロジェクトとしては、雑誌『POPEYE』一冊分を一枚の大きな和紙にし、それで照明を作るといったものだ。他にも、『美術手帖』とのコラボレーションとして、これまでの冊子を再生し、それを使った店舗用の什器を作る、といったプロジェクトも進んでいる。

リブや刺繍など、繊細な部分まで映し出されている。普段気に留めていない細かいディテールを改めて作品として見ることができて新鮮だった。
ブースで一際目立っていたTシャツが浮き出る和紙は、なんと簾桁(紙を漉く際に使う木枠にすだれなどがはめ込まれたもの)にTシャツを平置きした状態で紙を漉いたという。
「こうしてただのTシャツがアートになると、首元のリブがこんなにはっきり見えるんだとか、袖口はこうなっていたんだ、こんなロゴが入っていたんだと改めて気付かされますよね」(名尾手すき和紙 谷口弦さん)。
明治維新で大量生産の洋紙が入ってきた際に、それに対する「和紙」という言葉が生まれたが、それまでは「再生紙」という言葉はなく「環魂紙」と呼ばれていたのだそう。言葉の由来は、いらなくなった紙が蘇るというところから来ている。谷口さんの取り組みは、紙だけでなく工場で出た植物の屑で新しい紙を生み出し、ただのTシャツをアートに変え、まさに生まれ変わった、魂が蘇ったという表現がしっくりくる。元が何であったか分からない状態ではなく、使われた材料の存在感があることで、より1枚1枚が生きているように感じる。紙で漉かれたTシャツは写真や絵よりもずっと、Tシャツそのものがはっきりと写し出されているように見えた。 「“現代の紙屑屋”になりたいと思っています」と話してくれた谷口さんの笑顔が印象的だった。
大日本市には食品も多く出展されていた。
軽快なトークで試食を勧めて人気を集めていたのは奈良県の坂利製麺所だ。1984年の創業以来国産小麦100%で手延べ素麺、うどんの製造販売を行なっていた同社は「若い人たちに自分たちの製品を知ってもらい食べてもらうためには、もっと手軽に作れるようにしなくてはいけない」とフリーズドライの商品の開発をスタート。3年前に発表した、マグカップに商品を入れてお湯をそそぐだけで簡単ににゅう麺が作れるという「マグカップにゅう麺」が人気だ。今年3月から発売開始の新商品は、その名も「ニューメン」。

軽快なトークと共に手際よく「ニューメン」を作る株式会社坂利製麺所・常務取締役の坂口利勝さん。
「手延べ麺では不可能と言われていたお鍋一つで即席調理ができる逸品で、味にも強いこだわりがあります。国産小麦の味わいと手延べ麺のおどろきのツルツル感を融合した独特の太さに仕上げ、さらに、手延べ麺に入っている塩分を計算した特殊なあごだしを開発しました」(株式会社坂利製麺所 常務取締役 坂口利勝さん)。
500ccで5分茹で、茹で汁にあごだしを入れればでき上がってしまう。 2食入りで348円(税別)という安さも重要なポイント。

お話を聞いている内にあっと言う間に出来上がり、簡単で本格的な味に驚いた。

若い人も手に取りやすいポップなパッケージでギフトとしても人気だ。
「普段料理をしないような若い学生さんでも簡単に作れるので、1人暮らしのお家に常備しておいてもらったり、若いカップルで仲良く食べてもらえたら嬉しい。マグカップにゅう麺はマグカップとのギフト提案などもできる」(坂口利勝さん)など、具体的なシチュエーションが想定された商品開発で、今後も新しいアイディアが生まれそうだ。

ほっこりとした羊のパッケージがかわいい「ひなたのほしものがたり」。どれも素材の味がしっかり感じられる。
そんな新しいアイディアは、製造方法の発展だけでなく、素材の開拓によっても生まれる。
漬物用の干し大根の生産で日本一を誇る宮崎から出展していたのは乾燥食品の製造販売を行う合同会社フードマーク。かわいらしい羊のパッケージが若い女性にも喜ばれそうな「ひなたのほしものがたり」は20種類以上の様々な食材を乾燥させたもの。中でも1本の明太子のみを使用したというドライ明太子は他ではなかなか見かけない商品。多くの人が立ち止まっていた。

ドライ「たくあん」。味が凝縮されて、おつまみとしても喜ばれそうだ。
最初はマグロを使った「お魚ジャーキー」が始まりだそう。常温で長い期間保存でき、添加物も一切なく栄養が摂れるものを作りたいと考え、様々な商品が生まれた。魚は刺身や焼き魚などで食べることはあっても常温で食べることはなかなか難しい。乾燥食品にすれば常備食として置いておけるし、子どものお菓子やおつまみ、ご飯のお供としていつでも楽しむことができる。 新しい商品としては、おから茶やお湯で戻せる乾燥ごはん、パンなど。パンは表面に味をつけるラスクとは違い、浸して乾燥させるので軽い食感でしっかりした味が楽しめる。
老舗の工房や地方の職人にとっては、若い人とのタッチポイントや、もっと気軽に作品に触れてもらうきっかけが必要だ。

「陶芸ガチャガチャ」(1回200円)。普段、陶芸になかなか触れる機会のない人も、ついやってみたくなる。
福井県に越前焼の窯元を持つ伝統工芸士の宗倉克幸さんは、焼き物で木を表現したという「陶木」を展示。手に触れる感触が心地よく、雪の中で静かに立つ杉の木のような、どっしりとした温かみを感じる作品だ。丁寧に並べられた作品は、今回のような合同展示会では逆に近寄りがたい印象も与えてしまう。しかしそんな展示スペースの一角に「200円で1回」という貼り紙のされた「ガチャガチャ」が設置されていた。思わず200円を財布から取り出し、ダイヤルを回してしまった。中から出てきたカプセルを開けてみると、かわいらしい一輪挿しが。土や木など自然をそのまま表現したような越前焼とはまた違い、ポップな色や柄が親しみやすい。「気軽に焼き物に触れてほしい」という宗倉さんの考えから設置された楽しい仕掛けだった。

焼き物で木を表現した作品「陶木」。作られた場所を想像したくなる。

伝統工芸士の宗倉克幸さん。普段は福井県の工房で作品を作り続けている。
10代や20代の若い女性に好まれそうなポップでキャッチーな「おみくじろうそく」や「祈願蝋燭」を展開していたのは、同じく福井で慶応元年から和蝋燭を作り続けている株式会社小大黒屋商店だ。

おみくじの入った「おみくじろうそく」。手軽に購入できるサイズが魅力的だ。

季節に沿った絵柄の描かれた蝋燭。仏事だけでなく、カジュアルに和蝋燭を楽しめる。
蝋燭は普段、仏事で使われることがほとんどだが、付加価値を盛り込んでパッケージなどにもこだわり、手にとってもらいやすいように工夫されていた。昔ながらの「手描き絵ろうそく」は四季折々の花などがカラフルに描かれており、1本1本丁寧に作られているのが感じられた。 「昔は雪が降ってお花が見れない時、その代わりにお花が描かれた蝋燭を灯すという習慣があったんですよ」と教えてくださったのは営業の定兼吾郎さん。そういったエピソードは、手にとりやすいパッケージ以上に商品に価値を与えてくれる気がする。工芸品を若い人にもっともっと認知してもらうためには、そのような作り手の思いや昔ながらの風習などを伝える機会を作ることこそが重要なのではないか。

会場を回っている間にも続々とシールが集まっていた。
会場に設置されていた来場者人気投票には続々とシールが貼られていた。2日目である2月14日(木)のお昼の時点で多く票を獲得していたのは日本一の靴下生産量を誇る奈良で展開する、「チャリックス」だ。「チャリンコをこいでソックスがつくれる」とは一体どういうことだろうか。早速ブースへ向かってみると、来場者と思われる若い男性が、本当に自転車を漕いでいた!
運営元は株式会社創喜で、中川政七商店やその他アパレルブランドで取り扱う靴下を多く手がけている会社だ。1927年の創業から変わらず靴下を作り続けてきたが、もっとたくさんの人に靴下やニットのこと、作り方や素材などについて知ってほしいという思いからワークショップの企画をスタートした。
実際の工場で使っている編み機を使って、自転車を漕ぎながら靴下を作ることができるというもので、それが“ワークショップブランド”の「チャリックス」だ。

1本の糸で作られたような1筆書きのイラストが面白い。

参加者は好きな色を3色選ぶことができる。
好きな色の糸を3色選び、サイズもメンズ、レディースと選べる(体験は小学生ぐらいのお子様から可能)。工場ではモーターを使って動かしているが、自転車を漕いで動くように改造している。糸は色が選べるコットン3本以外に、白い糸が必ず2本入る。丈夫な和紙とあたたかいシルクだ。自転車を漕ぎながら編み機を動かすと、かかとの部分で編み方が変わる時に、ペダルを押し下げる感触が変わるのを実感できる。通常大人で片足5分程度で完成し、その後はつま先部分の処理をミシンと手作業で行う(つま先の処理は工場スタッフが行う)。「Made in○○」という自分の名前を書き込めるタグを付けてもらい、「自分で靴下が作れるなんて!」という喜びと楽しさも得られる。

両サイドの白い糸はシルクと和紙。中央の3色は自由に選べるコットンの糸だ。

一緒に取材をしたインターン生の柳川さんが体験してくれた。編み方が変わると、ペダルの重さが変わる。
「生産者として、もっと奥側のことを知ってほしい。みんな機械で簡単にできあがると思っているが、こうして素材にこだわって、編み方も工夫して、最後は手作業で仕上げている」とふだん工場で働いている担当者は話してくださった。
現在は平日に毎日工場で生産にあたり、土日に百貨店等でワークショップのイベントを実施している。通信販売の管理をする人手も必要で、日々大忙しだ。

最後の仕上げはミシンを使って手作業。靴下の構造や仕上げ方を説明しながら丁寧に仕上げてくれる。
「安く作られた商品もたくさん増え、ただ良いものを作るというだけでは売れなくなっている。若いデザイナーも興味を持ってうちに来てくれるが、ただきれいなデザイン画を描けるだけではだめで、作り方、構造、糸などの素材までちゃんと知っている人でないと商品を作っていくのは難しいんです。だからもっと、奥側のことも知ってほしい。いずれは観光産業にできないかと考えています。奈良に泊まりにきたついでに自転車を漕いで靴下を作れる。まだ工場でのワークショップイベントは実施できていないのですが、近いうちにやっていきたいです。できあがった靴下だけでなく、体験や知識を売っていけたらと思っています」。

出来上がった靴下はオリジナルのタグを付けて持って帰ることができる。柔らかくさらっとした生地が気持ちいい。

「チャリンコ」のハンドル部分にはハムスターの人形が応援してくれていた。
情報過多の昨今、インターネットで自社の製品を公開しても、検索してもらうきっかけがなければもはやその情報は届かない。結局は直接伝えることのできる機会をそれぞれが常に模索しており、その手段のひとつとして、本「大日本市」のような合同展示会は有効といえる。
一方、来場したショップオーナーやバイヤーの人たちにとっても、今回のように日本各地の商品を一度に見ることができる機会は貴重だ。実際に作り手とコミュニケーションを取ることで、商品が作られた場所やその土地の風景といった背景にあるストーリーを知ることができ、ただ店頭で商品に触れるよりもずっと価値を実感できる。

来場者に配られたオリジナルのトートバッグ。
同時期に開催されていた「ててて共同組合」による「ててて見本市」や、3月に開催予定の「COMMUNE」(セキユリヲが手がける「サルビア」主催)など、作り手と直接つながることのできる合同展示会は多く開催されている。会期中に一般開放日を設けるものも増えてきた。
今回お話した出展者の中には「ふだん田舎に引きこもって職人として過ごしている自分にとって、人前に出て自己主張するのは大変」という声もあったが、中川政七商店では地方の職人を対象とした研修も実施しており、情報発信の仕方や商品管理など、ビジネスにつなげる仕組み作りを学ぶことができる。「日本の工芸を元気にする!」をビジョンに掲げる同社の取り組みをきっかけに、ぜひご自身の育った場所の風景や人のことを伝えていってほしいと感じた。
【取材・文:堀坂有紀(『ACROSS』編集部)+柳川千恵(文化服装学院2年生)】