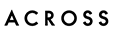きっかけは、00年に上梓した『批評の事情』(原書房)という本をつくっている時に遡ります。これは、90年代にデビュー、もしくはブレイクした批評家たちを紹介する本で、その顔ぶれは30代半ばから40代前半が中心でした。当時、担当編集者の大西さんと、世代論ではないんですが、批評家もある種「世代の断絶」ってあるよね、という話をよくしてたんです。批評家編はつくったから、今度はモノをつくる人編をやろうよ、っていう話になったのが、99年から00年。それから3年近くかかって、『平らな時代』という本にまとまりました。
もともと、『本とコンピュータ』という雑誌の編集委員をやってるんですが、ちょっと前の編集委員会の場で、筑摩の専務でもある松田哲夫さんとか、デザイン評論家の柏木博さんなどと話をしていたときに、松田さんが、本は老人メディアだから、(若い世代のことは)もう諦めた方がいいんじゃないか、と発言されたんです。まあ、それは一面ではそうなんですが、もしかすると世代や年齢などによって、本とかメディアに対する意識や価値観そのものが違うんじゃないか。そう思った時に、そこにどう線を引くかがテーマとして浮き彫りになってきたわけです。

「おたく世代」以降は、世界の認識の仕方が違う。

『平らな時代 おたくな日本の
スーパーフラット』(原書房)。
スーパーフラット』(原書房)。
隠しテーマは、「フラット、ユニット、データベース」
ひとつには、仮説として、『平らな時代』のなかの会田誠さんの項でも書きましたが、TVがうちに来た日を覚えている世代と生まれた時からあった世代とでは、メディアに対する感覚が違うはずだ、というのがありました。1960年代の前半をどう体験したかということです。
小熊英二さんの『<民主>と<愛国>』にあったように、1945年の敗戦からしばらくの間の日本の状況を、どこで何歳の時に、どういう状況で経験したかによって、似たような世代であっても、ぜんぜんものごとが違ってみえる、ということを踏まえ、60年代、70年代、80年代、そして90年代をどういう状況で体験してきたのかなどを、インタビューで直接確かめてみたい、という強い思いもありました。さらに、文字数無制限のロングインタビューということもやってみたかった。『批評〜』に比べると、ずいぶんと手間もかかり、且つボリュームのある本になりました。
小熊英二さんの『<民主>と<愛国>』にあったように、1945年の敗戦からしばらくの間の日本の状況を、どこで何歳の時に、どういう状況で経験したかによって、似たような世代であっても、ぜんぜんものごとが違ってみえる、ということを踏まえ、60年代、70年代、80年代、そして90年代をどういう状況で体験してきたのかなどを、インタビューで直接確かめてみたい、という強い思いもありました。さらに、文字数無制限のロングインタビューということもやってみたかった。『批評〜』に比べると、ずいぶんと手間もかかり、且つボリュームのある本になりました。

読書は「石蹴り」のようなもの。
ムツゴロウにはじまり…
ムツゴロウにはじまり…

ムツゴロウの同級生だった大江健三郎
を読むようになり…、サルトルやヴォ
ーヴォワールへ…
を読むようになり…、サルトルやヴォ
ーヴォワールへ…
読書は「石蹴り遊び」のようなもの
僕自身の体験を振り返ると、とにかく地味な子どもでした。小さい頃から少年少女文学全集的なものを親にねだって買ってもらい、毎日本ばかり読んでいました。父親が小学校の教員でしたから、一般家庭よりは本の多い家だったんだと思います。いわゆるジュニア小説、『あしながおじさん』や『赤毛のアン』とかは小学校の頃、スタンダールなんかは中学生のときに読んでましたね。三段組の筑摩版。文字が小さくてとても読みにくい本だったのを覚えています。本はよく読むけどスポーツは全然ダメ。身体も小さかったでし、なぜか子どもの頃から花粉症だったんですよ(笑)。
中学生の時に、畑正憲さんの『ムツゴロウの青春期』とか『ムツゴロウの結婚期』といったエッセイに夢中になりました。畑さんは学生の時は作家になりたかったそうなんですが、ある日作家になる夢を諦めるんです。「すごい才能の人を見つけたから僕は諦める」と言って。それが大江健三郎さん。なんと同級生で、東大学生新聞に書いてあった大江さんの記事を読み、きっぱり決心したという。畑さんが作家になるのを諦めるほどすごい作家ってどうなんだろう、ということで、大江健三郎を読みはじめた。
ほかにも、畑さんが北杜夫を尊敬しているというので、北さんをきっかけに、遠藤周作さんの狐狸庵先生シリーズとか、安岡章太郎さんの『なまけものの思想』とかを読みあさる。当時は「第三の新人」というのがブーム。その周辺のものも読みました。エッセイから入って、小説も読んだ。一方、大江健三郎さんが学生時代に夢中になったというサルトルとかボーヴォワールとかも読むようになる。
石蹴り遊びのようなもんですよ。1冊読んだらその中にヒントがあって、そこに関係のありそうな本をまた読む。別に学校の勉強と違って、成績がよくなるためとかじゃないですからね。無駄なことですから。そういう「無駄なことをする」というのはとても大事なことだと思います。もちろん、その時はまだ、書く仕事をするとか、本屋さんになるというようなことは全然考えていませんでした。
中学生の時に、畑正憲さんの『ムツゴロウの青春期』とか『ムツゴロウの結婚期』といったエッセイに夢中になりました。畑さんは学生の時は作家になりたかったそうなんですが、ある日作家になる夢を諦めるんです。「すごい才能の人を見つけたから僕は諦める」と言って。それが大江健三郎さん。なんと同級生で、東大学生新聞に書いてあった大江さんの記事を読み、きっぱり決心したという。畑さんが作家になるのを諦めるほどすごい作家ってどうなんだろう、ということで、大江健三郎を読みはじめた。
ほかにも、畑さんが北杜夫を尊敬しているというので、北さんをきっかけに、遠藤周作さんの狐狸庵先生シリーズとか、安岡章太郎さんの『なまけものの思想』とかを読みあさる。当時は「第三の新人」というのがブーム。その周辺のものも読みました。エッセイから入って、小説も読んだ。一方、大江健三郎さんが学生時代に夢中になったというサルトルとかボーヴォワールとかも読むようになる。
石蹴り遊びのようなもんですよ。1冊読んだらその中にヒントがあって、そこに関係のありそうな本をまた読む。別に学校の勉強と違って、成績がよくなるためとかじゃないですからね。無駄なことですから。そういう「無駄なことをする」というのはとても大事なことだと思います。もちろん、その時はまだ、書く仕事をするとか、本屋さんになるというようなことは全然考えていませんでした。
ディスコに行くこともなかった地味な大学生時代
高校生までは、人並み以上に本を読んでいるような気分でいたんですが、上京してみたら、もっと本を読んでて、もっと詳しい人がたくさんいた。田舎の高校生の自尊心なんて簡単にへし折られましたね。
大学を選んだ理由は、サルトルを日本に紹介した文学者のひとり、矢内原伊作先生の授業を直接受講したかったからです。サークルは哲学研究会。本を読むか、部室で酒を呑んでばかりという地味な学生でしたね。ディスコに行くこともありませんでした。あとはアルバイト。
マンガはダメなんですよね。音楽は、高校生の頃はみんなが陽水、拓朗、ユーミンとかいっている時代でしたが、僕は頭脳警察。大学生以降は、パンクとかニューウェーブの影響を受けました。
大学を選んだ理由は、サルトルを日本に紹介した文学者のひとり、矢内原伊作先生の授業を直接受講したかったからです。サークルは哲学研究会。本を読むか、部室で酒を呑んでばかりという地味な学生でしたね。ディスコに行くこともありませんでした。あとはアルバイト。
マンガはダメなんですよね。音楽は、高校生の頃はみんなが陽水、拓朗、ユーミンとかいっている時代でしたが、僕は頭脳警察。大学生以降は、パンクとかニューウェーブの影響を受けました。

『デュシャンは語る』
(ちくま学術文庫/99)
(ちくま学術文庫/99)
『セントラルアパート物語』
浅井慎平(集英社文庫/97年)
浅井慎平(集英社文庫/97年)
セゾン文化の洗礼を受けた世代
大学5年生の時に西武美術館でアルバイトをしていました。単位を全部取得して卒論だけ残して留年すると、学費が半額なんです。就職も決まってなくて、何となくの1年留年。その時は博物館の学芸員になろうと思ってたんです。それには現場の経験を積んだ方がいいよと言われたこともあり、何カ所かにアルバイトさせてくれってお願いしに行ったら、西武美術館だけがOKになった。後で調べたら、あそこは博物館法で定める博物館じゃなかったんですね。百貨店の催事場ですから(笑)。でも、当時の西武美術館は、現代美術のなかでは日本の最先端のことをやっていましたから正式な博物館かどうかなんてどうでもいい。毎日夢中で働きましたね。
1981年、軽井沢にセゾン現代美術館がオープンしたんですが、そのオーニングの時は学生アルバイトなのに1ヵ月ほど泊まり込みで働きました。オープニングはマルセルデュシャン展。上司が卒業後に百貨店受けるんだったら推薦してあげてもいいよ、と言ってくれたんですが、たまたま同じフロアにあるアールヴィヴァン(今のナディッフの前身)の人から、来ないかと誘われたのでそちらに就職することにしました。アールヴィヴァンは、世界の現代美術に関する情報ではピカイチの会社でしたからね。
最初は本店。池袋の勤務でしたが、その後、今はなき「六本木WAVE」の中に「ストアデイズ」という書店をオープンすることになり、そこにも勤務しました。六本木にオープンする前の1年間は、原宿のセントラルアパートの中の一室で営業していたので、一時は原宿に通ってました。あの頃のセントラルアパートはものすごい人たちがいっぱいいて、糸井重里さんの事務所や、浅葉克己さんの事務所があった。YMOとかシュガーベイブの大貫妙子さんとかもよく来ていたり、いつもいろんな人が集まってていました。原宿にものすごいパワーがあった時代。そんななか、僕はお客さんだった編集者の人に頼まれ、『宝島』などに書評を書くようになりました。会社もそういったことをパブリシティ効果の一貫としてか推奨していたので、いろんな雑誌に執筆するようになっていました。
1981年、軽井沢にセゾン現代美術館がオープンしたんですが、そのオーニングの時は学生アルバイトなのに1ヵ月ほど泊まり込みで働きました。オープニングはマルセルデュシャン展。上司が卒業後に百貨店受けるんだったら推薦してあげてもいいよ、と言ってくれたんですが、たまたま同じフロアにあるアールヴィヴァン(今のナディッフの前身)の人から、来ないかと誘われたのでそちらに就職することにしました。アールヴィヴァンは、世界の現代美術に関する情報ではピカイチの会社でしたからね。
最初は本店。池袋の勤務でしたが、その後、今はなき「六本木WAVE」の中に「ストアデイズ」という書店をオープンすることになり、そこにも勤務しました。六本木にオープンする前の1年間は、原宿のセントラルアパートの中の一室で営業していたので、一時は原宿に通ってました。あの頃のセントラルアパートはものすごい人たちがいっぱいいて、糸井重里さんの事務所や、浅葉克己さんの事務所があった。YMOとかシュガーベイブの大貫妙子さんとかもよく来ていたり、いつもいろんな人が集まってていました。原宿にものすごいパワーがあった時代。そんななか、僕はお客さんだった編集者の人に頼まれ、『宝島』などに書評を書くようになりました。会社もそういったことをパブリシティ効果の一貫としてか推奨していたので、いろんな雑誌に執筆するようになっていました。

日本で最も歴史あるSM雑誌、
『S&Mスナイパー』(ワイレ
ア出版)
『S&Mスナイパー』(ワイレ
ア出版)
そもそも、ものを書くことは恥ずかしいこと
その後、88年にアールヴィヴァンを退社するんですが、とくに次の仕事を決めていなかったので、お客さんの編集者の人が心配して、『SMスナイパー』というエロ本の仕事を紹介してくれたんです。次の日からはエロ本編集部でアルバイトとして働くことに。それが、エロ本仕事との出会いです。
多いときはアダルトビデオ月60本。撮影に立ち会ったりAV女優にインタビューしたり、ビデオ評を書いたりしてました。エロ本仕事は重要。大事にやっていこうと思っています。人に言えない仕事、田舎の親に言えない仕事を必ずやっていくようにしないとダメになる。そう思っているんです。恥ずかしいことをする。そういう仕事が大事。基本的に、ものを書いたりすることは恥ずかしいことですから、それをメディア業界だとかいって胸を張ったり傲慢になったらダメですよね。おてんとうさまをまともに見れないようなのが、この仕事なんです。
一般誌とエロ仕事、そしてもう1つの柱が、出版の流通に関すること。この3つのバランスが上手く保たれればいいなと思ってやてきたんですが、ここ数年は、エロ本の仕事っがめっきり減ってきて困ってるところです。あの業界は編集者が若いので、なかなか自分よりも年上の書き手に原稿を依頼しにくいのかもしれませんね。ただ単に年齢が違うということだけでなく、どこか分かりあえない溝がある。90年代半ば頃からかな。僕は98年に40歳になったんですが、ちょうどその頃くらいから、それぞれの局面において、「世代間の断絶」のようなものを感じるようになったというわけです。
多いときはアダルトビデオ月60本。撮影に立ち会ったりAV女優にインタビューしたり、ビデオ評を書いたりしてました。エロ本仕事は重要。大事にやっていこうと思っています。人に言えない仕事、田舎の親に言えない仕事を必ずやっていくようにしないとダメになる。そう思っているんです。恥ずかしいことをする。そういう仕事が大事。基本的に、ものを書いたりすることは恥ずかしいことですから、それをメディア業界だとかいって胸を張ったり傲慢になったらダメですよね。おてんとうさまをまともに見れないようなのが、この仕事なんです。
一般誌とエロ仕事、そしてもう1つの柱が、出版の流通に関すること。この3つのバランスが上手く保たれればいいなと思ってやてきたんですが、ここ数年は、エロ本の仕事っがめっきり減ってきて困ってるところです。あの業界は編集者が若いので、なかなか自分よりも年上の書き手に原稿を依頼しにくいのかもしれませんね。ただ単に年齢が違うということだけでなく、どこか分かりあえない溝がある。90年代半ば頃からかな。僕は98年に40歳になったんですが、ちょうどその頃くらいから、それぞれの局面において、「世代間の断絶」のようなものを感じるようになったというわけです。

文藝別冊『90年代J文学マップ』
(河出書房)。
(河出書房)。
「J文学」は90年代のセゾン系だった
90年代を「失われた10年」だったとよくいわれますが、その前のいい時代を知っている人が言うんだったらまだしも、10歳年下の人が、この10年ずっと失われっぱなしだったのかと思うと、かわいそうだな、とある日ふと思ったんです。88年に地価の暴落が始まり、メディアのなかでもバブル崩壊が意識されるようになるのが91年から92年。早い人は80年代の終わりに感じていたでしょうから、88年に20歳だった若者は、いちばん多感な青春時代に、世の中はずーっと下りっぱなし。もうダメだダメだって言われた世代と、登り坂を知っている世代では、世の中に対する感覚がぜったいに違う。そう確信したのが90年代の終わりでした。
「J文学」っていうキーワードが出てきたのも同じ頃です。悪口を言う人もいっぱいいましたが、基本的には、90年代の文学というものに線を引くと際立ったものが見えてくるだろう、と、編集者がつけたネーミングです。カテゴリーではなく、90年代の文学を「J文学」と言ってみる、ということ。個々の小説がいい、悪いということではなくて、こうやっていろんな物事の切り方を見せるのが文藝ジャーナリズムの仕事なんだから、当然それは支持すべきであるというのが僕の意見でした。
「世代の断絶」をまとめようという意志の根っこがあるとしたら、そこなのかもしれません。少し前に、『文藝別冊』に「J文学はセゾン系である」っていうエッセイを書いたことがあるんです。妙にウケが良かったんですけれども、ようは「共通の空気を吸った人」の話。スーパーフラットの考え方に繋がるのです。
「J文学」っていうキーワードが出てきたのも同じ頃です。悪口を言う人もいっぱいいましたが、基本的には、90年代の文学というものに線を引くと際立ったものが見えてくるだろう、と、編集者がつけたネーミングです。カテゴリーではなく、90年代の文学を「J文学」と言ってみる、ということ。個々の小説がいい、悪いということではなくて、こうやっていろんな物事の切り方を見せるのが文藝ジャーナリズムの仕事なんだから、当然それは支持すべきであるというのが僕の意見でした。
「世代の断絶」をまとめようという意志の根っこがあるとしたら、そこなのかもしれません。少し前に、『文藝別冊』に「J文学はセゾン系である」っていうエッセイを書いたことがあるんです。妙にウケが良かったんですけれども、ようは「共通の空気を吸った人」の話。スーパーフラットの考え方に繋がるのです。

90年放映の深夜番組『カノッサの屈辱』
(フジテレビ)。80年代のトレンドを
世界史に重ねたエンタテインメント番組。
その後放映された『ワーズワ−スの庭』
は04年CSにて再放送されるそうだ。
(フジテレビ)。80年代のトレンドを
世界史に重ねたエンタテインメント番組。
その後放映された『ワーズワ−スの庭』
は04年CSにて再放送されるそうだ。
『トリビアの泉』が流行るフラットな時代性
若い編集者と話をしていて「通じない」ことがある。それは、こっちが前提としている価値の体系みたいなものが「向こう」にはないから、個々の事象の重みも表層的に同じに見える。ものごとに対するヒエラルキーのなさ。価値体系のなさ。知ってるとか、持ってるとかが威張りに繋がらない。それはメディアの作り手の方にとっては、すごく仕事がやり辛いことです。脅かしっこが効かない。基本的にメディアの世界は脅かしっこで成り立ってますから。書評なんかそうじゃないですか。この本を今読んでおかないと恥ずかしいとか損だよというコンプレックスを煽るようなものがあるじゃないですか。それが成り立たないな、っていうのが実感としてありましたね。きっと音楽やファッションとかも同じだと思います。
価値の体系を身につけるが教養を身につけることであって、教養を身につけることが、階級の上昇と収入の上昇と同義語だった時代があったと思うんですが、それが90年代を通して崩壊してまったたのかもしれません。
『トリビアの泉』が出てきたのが非常に象徴的で、その昔、小山薫堂さんのデビュー作だった『カノッサの屈辱』とか、松山猛さんの『ワーズワースの庭』とかは、価値体系に依存した形の「これ知ってるかい?」っていうのだったわけですが、『トリビアの泉』は違う。どんな事象も等価で平べったく並んでる。
価値の体系を身につけるが教養を身につけることであって、教養を身につけることが、階級の上昇と収入の上昇と同義語だった時代があったと思うんですが、それが90年代を通して崩壊してまったたのかもしれません。
『トリビアの泉』が出てきたのが非常に象徴的で、その昔、小山薫堂さんのデビュー作だった『カノッサの屈辱』とか、松山猛さんの『ワーズワースの庭』とかは、価値体系に依存した形の「これ知ってるかい?」っていうのだったわけですが、『トリビアの泉』は違う。どんな事象も等価で平べったく並んでる。

ファミコン世代の大ベストセラー
『ゴクドー』シリーズ。各巻50
万部は下らないという。
『ゴクドー』シリーズ。各巻50
万部は下らないという。
若者は本を読まなくなった、という誤解
さて、今どきの10代はほんとうに本を読まなくなったのか、という命題について。決してそんなことはありません。統計ではむしろ70代とか60代以上の高齢者の方が読んでない。10代の子が本を読んでいるように見えないのは、彼等が読んでいるのは、中高年からみると、本に見えないからなんです。
たとえば、電撃系のファンタジー文庫は、見えない巨大なマーケットになっていて、中村うさぎさんの場合、お買い物エッセーなんかよりも、『ゴクドーくん漫遊記』みたいなジュニア向けのファンタジー小説の方が数十倍読まれている。上遠野浩平さんの『ブギ−ポップは笑わない』も20何刷り。ものすごく売れている。といっても、こういう分野は読む世代をかなり選びますから、その年齢層の人口比からするとかなりの比率で読まれていることになる。
これらはファミコンで育った世代。世界名作全集で育った世代のさらに次の世代です。そういう意味では、携帯電話とか、あとは最近のデジタル家電なんかも価値観の形成に大きな影響を与えるメディアといってもいいかもしれません。そういえば、『囚人狂時代』の著者、見沢知康さんをインタビューしたことがあるんですが、刑務所から出てきていちばん驚いたのが、家電製品が喋ることだって言ってました(笑)。
たとえば、電撃系のファンタジー文庫は、見えない巨大なマーケットになっていて、中村うさぎさんの場合、お買い物エッセーなんかよりも、『ゴクドーくん漫遊記』みたいなジュニア向けのファンタジー小説の方が数十倍読まれている。上遠野浩平さんの『ブギ−ポップは笑わない』も20何刷り。ものすごく売れている。といっても、こういう分野は読む世代をかなり選びますから、その年齢層の人口比からするとかなりの比率で読まれていることになる。
これらはファミコンで育った世代。世界名作全集で育った世代のさらに次の世代です。そういう意味では、携帯電話とか、あとは最近のデジタル家電なんかも価値観の形成に大きな影響を与えるメディアといってもいいかもしれません。そういえば、『囚人狂時代』の著者、見沢知康さんをインタビューしたことがあるんですが、刑務所から出てきていちばん驚いたのが、家電製品が喋ることだって言ってました(笑)。

93年の話題作、アントニオ・
ネグリとマイケル・ハ−トの
『帝国』。
ネグリとマイケル・ハ−トの
『帝国』。
スーパーフラットの次?
自分のなかでは、「時代をみる」みたいなことでは、取りあえず『批評〜』と『平ら〜』でいいかな、って思っています。今気になるのは、「平らの次は凹凸か?!」なんていうことではなく、去年の1月か2月に、アントニオ・ネグリとマイケル・ハ−トの『帝国』という本が話題になりましたが、多国籍企業とグローバリズムの問題。もしかしたら、企業のそういうのをテーマにすることもあるかもしれない。
グローバリズムっていうと、アメリカ型のルールを他の国に押し付ける、っていうふうに思われがちだけども、問題はそれだけじゃない。たとえば、洋服であれば、ヨーロッパのブランドみたいなものが、ひとつの美的感覚のグローバルスタンダードだっていってるわけじゃないですか。それは、ヨーロッパの貴族社会における文化の文脈みたいのが、常に座標軸としてあるわけですよね。でも、少しずつ、その座標軸が変わってきてるんじゃないかと感じるんです。
まあ、それがスーパーフラットの次になるのかどうかはよくわかりません。ただ、あんまり分かりやすくしてしまうと、スターウォ−ズの話みたいになってしまいますから(笑)。1、2、3があって、スーパーフラットがエピソード4あたりかな、なんていうことになりかねない!
モダニズムの問題と多国籍企業の問題と、グローバリズムの問題を繋いで考えることができれば、なんか違った見方ができるかもしれないな、って思いますね。軍事はあまり生活に密着した話ではありませんが、多国籍企業とグローバリズムは生活に密着した話ですよね。美しい生活をしたい、快適な生活をしたい、っていうこととすごく結びつくこと。あ、でもその前にエロ本仕事をもう少し増やしたいですね。
グローバリズムっていうと、アメリカ型のルールを他の国に押し付ける、っていうふうに思われがちだけども、問題はそれだけじゃない。たとえば、洋服であれば、ヨーロッパのブランドみたいなものが、ひとつの美的感覚のグローバルスタンダードだっていってるわけじゃないですか。それは、ヨーロッパの貴族社会における文化の文脈みたいのが、常に座標軸としてあるわけですよね。でも、少しずつ、その座標軸が変わってきてるんじゃないかと感じるんです。
まあ、それがスーパーフラットの次になるのかどうかはよくわかりません。ただ、あんまり分かりやすくしてしまうと、スターウォ−ズの話みたいになってしまいますから(笑)。1、2、3があって、スーパーフラットがエピソード4あたりかな、なんていうことになりかねない!
モダニズムの問題と多国籍企業の問題と、グローバリズムの問題を繋いで考えることができれば、なんか違った見方ができるかもしれないな、って思いますね。軍事はあまり生活に密着した話ではありませんが、多国籍企業とグローバリズムは生活に密着した話ですよね。美しい生活をしたい、快適な生活をしたい、っていうこととすごく結びつくこと。あ、でもその前にエロ本仕事をもう少し増やしたいですね。

自宅ができるまでをまとめた
『狭くて小さいたのしい家』。
(原書房/2004/8)
『狭くて小さいたのしい家』。
(原書房/2004/8)