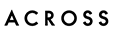中西:わたしと武内はエスモードの先輩後輩という関係なんですが、武内の卒業制作のモデルをしたことが最初の出会いでした。話をしてみると、表現するものは違うけどカンカクは近いものを感じて、何かいつか面白いことをいっしょにできそうな気がしたのです。
武内:96、97年頃ですから、着物とか和柄が流行っていた頃です。それぞれ卒業後は会社に入って服づくりを学びました。僕はコム・デ・ギャルソン。1年後に卒業した中西はサンエーインターナショナル。
金森:その後、2人が最初に発表した展覧会に行ったのが私が知り合ったきっかけです。レナウンの跡地で開催された「今日自由展」というアートイベントです。当時、私はリトルモア・ギャラリーの企画を担当していたので、いろんな作品を探していたところだったんです。この展覧会はもともとは別の作品を観に行ってたんですが、偶然彼らに出会い、ものすごく感動した!
もちろん、いろんな作品を観て感動することはあるんですけど、彼等の作品を観たときには、感動もしたんですが、なにやら他人ごとという気がしなくて。この人たちが次につくるものは何だろう、っていうか、この次ぜったいになんかつくんなきゃいいけないし、その次につくるものは自分がいちばん観たいものだ!っていう理由のない確信がありました。じゃあ、そのために、自分ができることはなんなんだろう、ってそこから考えたのがきっかけで、今こうなっているという感じですね。

シアタープロダクツ初めてのショップ。
ファサードはなんと木製の椅子。
ファサードはなんと木製の椅子。
3人の出会い、「ぜったいになんかつくなきゃいけない!」

2001年に初めて行った展示会。
テーマは「剥がす」。
テーマは「剥がす」。
「洋服をつくり続ける劇団」の誕生
武内:もともと僕は特に洋服にものすごく興味があったというわけではありません。というよりも、どちらかというと興味がない方だったかもしれない(笑)。高校生の時に、洋服屋の販売員の方に友だちがいたりして、人並みに洋服に関心を持つようになりましたが、それでも学生の時は貧乏だったので、そんなにたくさん買えないし(笑)。でも、買えないなら自分でつくろう、という気持ちにはなったわけでもありませんね。
高校を卒業して、空間デザインとかプロダクトデザインのようなものをやりたくて上京しました。でも結果的になんとなく服をつくる学校に入ってしまったという感じですね、今振り返ると。でも、洋服をつくることが向いてるのかもな、って気づきはじめたころでもあったので、没頭できた楽しい学生生活でしたね。
中西:私はすごく小さい頃から服はすごく好きだったんですが、特に個性的なファッションをする子どもだったということはありません。洋服をつくろうって思ったというか、将来洋服をつくるだろうなあとなんとなく思ったのは小学校のころでした。うんと小さい時に、お気に入りの洋服があって、でもTシャツと短パン、みたいなしょぼいものなんですが(笑)。よく覚えていませんが、こだわりはいくつもあったような気がしますね。それを着ていることが、とにかく嬉しかった。そんな単純な心への作用がおもしろくて服をつくっているのかもしれないですね。
誰にでも小さい時に感動したことで今でもときどき思い出す瞬間ってあるじゃないですか。
そんなふうに心が動くようなことを、感じ取ることができる心身でありたいといつも思っていますが、その感動を表現して、人に伝える手段がわたしにとっては洋服だったようです。
武内:服を中心にして中西と意気投合したのが99年ごろ。洋服を空間的に、立体的に表現するパフォーマンス的なアプローチをやっていようと、2人で「カプセルリ」というユニットを結成し、たまたま知り合いから出展しないかと声をかけてもらい「今日自由展」に参加したんです。タイトルは「タンプトック展」。予想以上に評判が良く、各地を巡回展示することになりました。
金森:その後、シアタープロダクツの結成は瞬時の出来事でした。
武内:「カプセルリ」としては、ミュージシャンの衣装をつくる仕事が入ったり、蜷川幸雄さん演出の『三文オペラ』の衣装を手がけたりもしていたんですが、なんかふつふつと沸き上がる思い、表現欲求みたいのがあって。だけれど、次どうしていいのかわからなくて、いろんな人に相談していた時期で、どうしたらいいんだろう、って出会ったばかりの金森ともそういう話になった。
金森:なんだかいっしょになって、どうしたらいいんだろう、っていって考えてみていたんです。その後、いろんな偶然とかが重なって、これなら会社がつくれるし、つくっちゃった方がいいんじゃないか、みたいな感じであっという間に決まっていったんです。そうと決まったら、名前を決めなくちゃ!ってことに。
武内:「シアター」というのは使いたいよね、というのはみんな即一致。
金森:「シアター」という単語と別な単語をいろいろ組み合わせてみて、結局「プロダクツ」がしっくりきた、というわけです(笑)。
高校を卒業して、空間デザインとかプロダクトデザインのようなものをやりたくて上京しました。でも結果的になんとなく服をつくる学校に入ってしまったという感じですね、今振り返ると。でも、洋服をつくることが向いてるのかもな、って気づきはじめたころでもあったので、没頭できた楽しい学生生活でしたね。
中西:私はすごく小さい頃から服はすごく好きだったんですが、特に個性的なファッションをする子どもだったということはありません。洋服をつくろうって思ったというか、将来洋服をつくるだろうなあとなんとなく思ったのは小学校のころでした。うんと小さい時に、お気に入りの洋服があって、でもTシャツと短パン、みたいなしょぼいものなんですが(笑)。よく覚えていませんが、こだわりはいくつもあったような気がしますね。それを着ていることが、とにかく嬉しかった。そんな単純な心への作用がおもしろくて服をつくっているのかもしれないですね。
誰にでも小さい時に感動したことで今でもときどき思い出す瞬間ってあるじゃないですか。
そんなふうに心が動くようなことを、感じ取ることができる心身でありたいといつも思っていますが、その感動を表現して、人に伝える手段がわたしにとっては洋服だったようです。
武内:服を中心にして中西と意気投合したのが99年ごろ。洋服を空間的に、立体的に表現するパフォーマンス的なアプローチをやっていようと、2人で「カプセルリ」というユニットを結成し、たまたま知り合いから出展しないかと声をかけてもらい「今日自由展」に参加したんです。タイトルは「タンプトック展」。予想以上に評判が良く、各地を巡回展示することになりました。
金森:その後、シアタープロダクツの結成は瞬時の出来事でした。
武内:「カプセルリ」としては、ミュージシャンの衣装をつくる仕事が入ったり、蜷川幸雄さん演出の『三文オペラ』の衣装を手がけたりもしていたんですが、なんかふつふつと沸き上がる思い、表現欲求みたいのがあって。だけれど、次どうしていいのかわからなくて、いろんな人に相談していた時期で、どうしたらいいんだろう、って出会ったばかりの金森ともそういう話になった。
金森:なんだかいっしょになって、どうしたらいいんだろう、っていって考えてみていたんです。その後、いろんな偶然とかが重なって、これなら会社がつくれるし、つくっちゃった方がいいんじゃないか、みたいな感じであっという間に決まっていったんです。そうと決まったら、名前を決めなくちゃ!ってことに。
武内:「シアター」というのは使いたいよね、というのはみんな即一致。
金森:「シアター」という単語と別な単語をいろいろ組み合わせてみて、結局「プロダクツ」がしっくりきた、というわけです(笑)。

毎回独自で開発するテキスタイルは
もちろんのこと、その技法にもこだ
わりが。
もちろんのこと、その技法にもこだ
わりが。
僕らの世代が考える「国籍のアイデンティティー」というもの。
武内:服をつくっている、という点では他のアパレルメーカーと同じなんだけど、どこか馴染んでないと言われる。
金森:海外ではロンドンと香港、台北のセレクトショップに卸しています。意識的ではないんですけど、これまでに表出してきている「日本のデザイン」に対する期待からは自由でありたいです。というか、私は74年で、武内が75年、中西が77年生まれなんですが、自分たちの世代的な感覚からすると、今の時代、それは必然的なものだと思うんです。
うまく言葉にならないんですが、日本から発信するべきだった貯金みたいなものを表現するのはひとしきり終わったかんじがして。
そういった既に発信された日本のデザインのアイデンティティのようなものも、外に存在するもの、ひとつの要素として既に私たちのまわりにある。「和」的なものの表現もそうですけど、もっと最近のところまで来ちゃうと、アニメとかゲームとかをモチーフとして表現するキャラクターとかがいっぱい登場しているじゃないですか。日本の現状からして当然あるべきアウトプットだと思うんですけど、わたしたちの現状は、その後にひろがる景色です。
中西:自分たちがどうかっていうのは、なかなか客観的に見るのは難しいし、ずっと服をつくる側にいて、外側からあまり見ることなくきてしまっているかもしれないんですけど(笑)。たしかに素敵な洋服をつくる方たちがあっちこっちにいるんですが、すばらしいなあ、ということを感じられることが少なくなっているような気がします。素敵だな、でもなんか知ってる、何処かで見たな、って思ってしまうことが少なくない。かといって、自分たちが奇をてらっているつもりはまったくないんですが、でも、つくっている側からすると、「知ってるなんて思わせない!」っていう強い思いはありますね。
武内:ファッション業界は今あまり幸せな状態じゃないような気がしますね。というか、そろそろ危機じゃないかなって思いませんか? 「トレンド」というものが、あまりにも安易になぞられ過ぎている。分かりやすく表現され過ぎているっていうんでしょうか。本当の意味でのデザイナーが不在の時代のような感じもしますね。
「壊して構築すること=モード」だと思い込んでいる人たちがすごく多い。でも、本当はいろんな時代を経た価値観がいっぱいあって、それはそのなかのひとつでしかない。じゃあ、何だろう?ということをいつも考えていて、シアタープロダクツの命題なのかもしれません。
金森:海外ではロンドンと香港、台北のセレクトショップに卸しています。意識的ではないんですけど、これまでに表出してきている「日本のデザイン」に対する期待からは自由でありたいです。というか、私は74年で、武内が75年、中西が77年生まれなんですが、自分たちの世代的な感覚からすると、今の時代、それは必然的なものだと思うんです。
うまく言葉にならないんですが、日本から発信するべきだった貯金みたいなものを表現するのはひとしきり終わったかんじがして。
そういった既に発信された日本のデザインのアイデンティティのようなものも、外に存在するもの、ひとつの要素として既に私たちのまわりにある。「和」的なものの表現もそうですけど、もっと最近のところまで来ちゃうと、アニメとかゲームとかをモチーフとして表現するキャラクターとかがいっぱい登場しているじゃないですか。日本の現状からして当然あるべきアウトプットだと思うんですけど、わたしたちの現状は、その後にひろがる景色です。
中西:自分たちがどうかっていうのは、なかなか客観的に見るのは難しいし、ずっと服をつくる側にいて、外側からあまり見ることなくきてしまっているかもしれないんですけど(笑)。たしかに素敵な洋服をつくる方たちがあっちこっちにいるんですが、すばらしいなあ、ということを感じられることが少なくなっているような気がします。素敵だな、でもなんか知ってる、何処かで見たな、って思ってしまうことが少なくない。かといって、自分たちが奇をてらっているつもりはまったくないんですが、でも、つくっている側からすると、「知ってるなんて思わせない!」っていう強い思いはありますね。
武内:ファッション業界は今あまり幸せな状態じゃないような気がしますね。というか、そろそろ危機じゃないかなって思いませんか? 「トレンド」というものが、あまりにも安易になぞられ過ぎている。分かりやすく表現され過ぎているっていうんでしょうか。本当の意味でのデザイナーが不在の時代のような感じもしますね。
「壊して構築すること=モード」だと思い込んでいる人たちがすごく多い。でも、本当はいろんな時代を経た価値観がいっぱいあって、それはそのなかのひとつでしかない。じゃあ、何だろう?ということをいつも考えていて、シアタープロダクツの命題なのかもしれません。

04年2月21日のオープニングレセプ
ション。若者から業界人まで幅広い。
ション。若者から業界人まで幅広い。

今回帽子は神戸の老舗メーカーと共同
で制作。「元気なお嬢様スタイル」は
80年代生まれの若者に絶大な人気。
で制作。「元気なお嬢様スタイル」は
80年代生まれの若者に絶大な人気。

前回からコレクションにテーマを設定。
今春夏のテーマは「大自然・前編」。
今秋冬は「大自然・後編」。
今春夏のテーマは「大自然・前編」。
今秋冬は「大自然・後編」。
「繁華街のビル」という空間で表現できること。
金森:今春でコレクションは5回目、ショーは2回目になるんですが、最初のコレクションでは「剥がして着る服」を発表しました。ニードルパンチの技法を使ってフラットにくっついたジャケットや、シート状のものにくっついたTシャツをつくったのですが、お客さんはそこから一枚一枚バリバリッてはがして買ってってもらったりもしました。2回目は、洋服のもつ大切な要素である装飾性を、オリジナルのジャガード生地などで表現しました。で、次は「より洋服に(距離的に)近付く」ということで、ディテールへのこだわりを際立たせるコレクションを作り、そして、初のファッションショー形式となった03A/Wでは、オフィス什器メーカーのショールームで「制服 for the O.L.」を発表しました。前回の04S/Sは大自然がモチーフ、テーマが「前編」です。そしていま「後編」にとりかかっています。
金森:服のデザインは基本的に武内と中西の2人が決めています。私は、その前とその後をどうするか、人間と空間、そして服がどんなふうに関わっていて、今何をどう表現できるのか、というのが課題。
武内:最初は展示会だけでやってたんですが、今はふつうに服つくってショーもやって、展示会やって、ときどき催事もやって、セールもやって、また展示会をやって、と他のアパレルメーカーさんと同じことをやっているんですが、なんか馴染んでないって言われることが多いですね。ロンドンのショップでは馴染んでるってよく言われるのに(笑)。
金森:すべてにおいて、いちいち面白がってやっている。ハリキリ過ぎなんです。(笑)
武内:今年はショップをつくることにした。しかも渋谷のど真ん中。
金森:繁華街っていうか、賑わっているところに出したいっていうのがあったんです。しかも、できるだけ雑多なところ。他の街も探したんですがなかなかなかった。そんな折、渋谷のゼロゲートの話があり。渋谷の繁華街のど真ん中にあるガラスのハコで、まとまった世界観が表現できる場所がいいな、って思った。
武内:これまでもショーの会場選びなど空間は重要でした。より面白い空間、場所、街っていうのにはこだわりました。「繁華街」という新しい切り口で、新しいシアタープロダクツが表現できればいいな、と思ったんです。
金森:初めてのショップです。商品も去ることながら、内装をどうしよう、ってみんなで話し合った結果、今のようなスタイルになりました。この椅子でつくった壁は、工事のことをいろいろと詰めていくうちに、そういえば、椅子の素材まんまを輸入し、倉庫にたくさん持っている方がいたことを思い出したんです。それで武内が、そうだ、椅子を積み上げよう、って言い出した(笑)。ふつうだったら、ガラスとか金属とかの壁をつくるんでしょうけど、ゆくゆく出て行った時に、それらがゴミになってしまうより、あとで使えるものでできているほうがいいですし。
武内:そういえば、床材に樹脂を流し込んだらどうなるんだろう、って言ったのも僕だったかも。でも、これもすごく評判がいいんですよ。ものすごく光沢があるのに丈夫で傷になりにくい。もっと他のショップも使ったらいいのに。
金森:椅子は全部で125個、だったと思うんですけど(笑)。全部にシリアルナンバーがついていて、1つ2万8,000円。人気のある形は予約でいっぱいなんです。
武内:え、どの形?
金森:背もたれのところがユルくカーブしているやつ。
中西:あー、あれね。
金森:あと、週に1回、コデマリイという生きているマネキンが店内に居ます。私たちも、順番店頭で接客しています。
武内:ここ1年はゼロゲートで頑張ろうって思っています。
金森:もうちょっと人気が出てもいいよね、なんて思ったりして。
全員:(大笑)。
金森:服のデザインは基本的に武内と中西の2人が決めています。私は、その前とその後をどうするか、人間と空間、そして服がどんなふうに関わっていて、今何をどう表現できるのか、というのが課題。
武内:最初は展示会だけでやってたんですが、今はふつうに服つくってショーもやって、展示会やって、ときどき催事もやって、セールもやって、また展示会をやって、と他のアパレルメーカーさんと同じことをやっているんですが、なんか馴染んでないって言われることが多いですね。ロンドンのショップでは馴染んでるってよく言われるのに(笑)。
金森:すべてにおいて、いちいち面白がってやっている。ハリキリ過ぎなんです。(笑)
武内:今年はショップをつくることにした。しかも渋谷のど真ん中。
金森:繁華街っていうか、賑わっているところに出したいっていうのがあったんです。しかも、できるだけ雑多なところ。他の街も探したんですがなかなかなかった。そんな折、渋谷のゼロゲートの話があり。渋谷の繁華街のど真ん中にあるガラスのハコで、まとまった世界観が表現できる場所がいいな、って思った。
武内:これまでもショーの会場選びなど空間は重要でした。より面白い空間、場所、街っていうのにはこだわりました。「繁華街」という新しい切り口で、新しいシアタープロダクツが表現できればいいな、と思ったんです。
金森:初めてのショップです。商品も去ることながら、内装をどうしよう、ってみんなで話し合った結果、今のようなスタイルになりました。この椅子でつくった壁は、工事のことをいろいろと詰めていくうちに、そういえば、椅子の素材まんまを輸入し、倉庫にたくさん持っている方がいたことを思い出したんです。それで武内が、そうだ、椅子を積み上げよう、って言い出した(笑)。ふつうだったら、ガラスとか金属とかの壁をつくるんでしょうけど、ゆくゆく出て行った時に、それらがゴミになってしまうより、あとで使えるものでできているほうがいいですし。
武内:そういえば、床材に樹脂を流し込んだらどうなるんだろう、って言ったのも僕だったかも。でも、これもすごく評判がいいんですよ。ものすごく光沢があるのに丈夫で傷になりにくい。もっと他のショップも使ったらいいのに。
金森:椅子は全部で125個、だったと思うんですけど(笑)。全部にシリアルナンバーがついていて、1つ2万8,000円。人気のある形は予約でいっぱいなんです。
武内:え、どの形?
金森:背もたれのところがユルくカーブしているやつ。
中西:あー、あれね。
金森:あと、週に1回、コデマリイという生きているマネキンが店内に居ます。私たちも、順番店頭で接客しています。
武内:ここ1年はゼロゲートで頑張ろうって思っています。
金森:もうちょっと人気が出てもいいよね、なんて思ったりして。
全員:(大笑)。