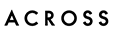体験型学習、いわゆるワークショップがここ数年注目されている。弊誌も授業という形で協力した「シブヤ大学」(06年9月開講)をはじめ、アートと文化に特化した講座を展開する「ウラハラ藝大」(07年12月開講)など、新規参入も盛んだ。そんななか、メジャーではないものの、口コミで広がり、チケットを販売するとたちまち完売してしまう人気のワークショップがある。その名は『Dialog in the Dark(ダイアログ・イン・ザ・ダーク)』。上下左右がまったく分からない真っ暗な空間を、目の不自由な方の案内のもと、聴覚、嗅覚、触覚、味覚など視覚以外の感覚を使って体験するというもの。第9回目となる今回、港区赤坂の廃校を会場に07年9月13日〜07年12月19日まで開催されたので取材した。
ダイアログ・イン・ザ・ダーク(以下、DID)とは、1989年、ドイツのアンドレアス・ハイネッケ博士のアイデアで生まれ、現在ヨーロッパを中心に20カ国70都市で開催、既に200万人が体験しているワークショップ形式の展覧会である。障害者の疑似体験のような福祉的イベントとしてではなく、視覚障害者と健常者の「こころのバリアフリー」を体験する機会を提供するこのプロジェクトは、開催国や地域によって、ローカル・スタッフと共同でコンセプトをローカライズするのが特徴でもある。
日本では、NPO法人ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンが運営。代表の金井真介さんは、1993年にDIDについての記事を新聞で知り、早速ハイネッケ博士に手紙を出し、日本での運営権を取得したのだそうだ。ユニバーサルデザインやバリアフリーへの理解や認知度が低い当時の日本での実現には時間がかかったが、1999年に東京ビッグサイトで第1回を開催。徐々に規模を拡大しながら、年に一度のペースで開催を重ねるまでに成長したというわけだ。04年からは TBSラジオとのタイアップで開催している。

会場となった(旧)港区立赤坂小学校。

会場入り口。真っ暗な空間が
この後ろ側に広がっている。
この後ろ側に広がっている。

NPO法人ダイアログ・イン・ザ・
ダーク・ジャパン
代表の金井真介さん
ダーク・ジャパン
代表の金井真介さん

今回は90日間で約9,000人が参加。2日間の開催で222人が参加した第1回目と比べると、約9倍へと集客も拡大。体験者の延べ人数は3万人と、認知度の高まりに期待が寄せられる。これまでの開催地は東京、神戸、仙台などだが、他にも大学や病院に出向いて行った「ショーケース」や、「子どものためのワークショップ」なども展開してきた。
「DIDは、『イン・ザ・ダーク』の部分が集中的にスポットを浴びていますが、暗闇でのダイアログ、対話がテーマです。暗闇との対話、参加メンバーとの対話、視覚障害者とのフラットな対話、そして自分との対話。バーチャルな森のシーンでも、そこにある落ち葉を触ったり匂いを嗅いだりすると、自分の記憶や経験にフィードバックできるんですよね。情報を足していったり、情報をかけ算していって刺激を与えるのではなく、このプロジェクトは情報をリセットして自らの記憶と対話するというのが面白さのひとつです。」(金井さん)。
参加者の75%は女性で、その多くが20〜30代。職業は会社員を中心に学生や主婦などさまざま。チケット確保が難しいため、仕事を休んで平日に参加する人も少なくないという。定員8人のグループにひとりの案内役がついて、1時間半かけて会場内を回る。1日に12〜15ユニットが参加する形式だ。
「入る前には緊張した面持ちである意味孤立していた人たちが、プログラムを終えて出てくると、みんな昔から友だちだったように会話している。トンネルを抜けてきた参加者の目の輝きを見る時が、人はすごいなと思う瞬間です。暗闇では、見えている時の区別や差別を取り払い、誰とでもフラットな関係で、素の自分となって話し、感じられます。全然知らない人との間に自然と役割ができ始めて、互いに助け合える。発案者のハイネッケが言うように、『暗闇は人をもとに戻すメディア』なんです。」(金井さん)
「DIDは、『イン・ザ・ダーク』の部分が集中的にスポットを浴びていますが、暗闇でのダイアログ、対話がテーマです。暗闇との対話、参加メンバーとの対話、視覚障害者とのフラットな対話、そして自分との対話。バーチャルな森のシーンでも、そこにある落ち葉を触ったり匂いを嗅いだりすると、自分の記憶や経験にフィードバックできるんですよね。情報を足していったり、情報をかけ算していって刺激を与えるのではなく、このプロジェクトは情報をリセットして自らの記憶と対話するというのが面白さのひとつです。」(金井さん)。
参加者の75%は女性で、その多くが20〜30代。職業は会社員を中心に学生や主婦などさまざま。チケット確保が難しいため、仕事を休んで平日に参加する人も少なくないという。定員8人のグループにひとりの案内役がついて、1時間半かけて会場内を回る。1日に12〜15ユニットが参加する形式だ。
「入る前には緊張した面持ちである意味孤立していた人たちが、プログラムを終えて出てくると、みんな昔から友だちだったように会話している。トンネルを抜けてきた参加者の目の輝きを見る時が、人はすごいなと思う瞬間です。暗闇では、見えている時の区別や差別を取り払い、誰とでもフラットな関係で、素の自分となって話し、感じられます。全然知らない人との間に自然と役割ができ始めて、互いに助け合える。発案者のハイネッケが言うように、『暗闇は人をもとに戻すメディア』なんです。」(金井さん)

《インタビュー・右/主婦》
目に見えることでもできないことが
多いとわかった。
《インタビュー・左/大学生》
余計なものを取り払うことができた。
目に見えることでもできないことが
多いとわかった。
《インタビュー・左/大学生》
余計なものを取り払うことができた。

《インタビュー・上/会社員》
日常以上にコミュニケーションを
とれるのが楽しかった。
《インタビュー・下/小学生》
手で触ってみたり、声をよく聞い
たりした。
日常以上にコミュニケーションを
とれるのが楽しかった。
《インタビュー・下/小学生》
手で触ってみたり、声をよく聞い
たりした。
リピーターも多く、なかには会期中に何度も参加する人もいるという。「同じハードに何回入っても、メンバーのバランスやアテンドによって変わるので、まったく同じには絶対になりません。エンターテイメントではない、筋書きのないライブなんです」(金井さん)。
アンケートを見ると、「みんなに体験してほしい」という意見が多く、実際、参加者の大半が友人・知人からのクチコミというのにも頷ける。
また、この、「五感のバランス」を取り戻す場をより多くの人に体験してもらいたいという思いと、視覚障害者の安定した雇用機会を確保しようとという狙いから、DID日本常設準備委員会を設置。既に、全盲を条件としたアテンドバンクも設立され、DIDの運営に関わるライセンスを交付したところだという。現在登録者は約30人、うち10数人が今回のアテンドとして関わった。3年前からアテンドを務める木下さんは「DIDに関わることで、自分たちが普段何気なく生活していることに、もう少し胸をはっていいのかなと思えるような、気持ちの切り替えがありました。今後もできる限り手伝いをしていきたいと思います」と話す。
「このプロジェクトには、高齢化社会のデザインやこれからの世の中の仕組みへのヒントが隠されているのではないでしょうか。今後、常設展示が実現しても消費される『商品』ではなく、100年続くような社会の中の『仕組み』にするにはどうしたらいいか考えているところです」(金井さん)。
[取材・文/笠原桐子+『ACROSS』編集室]
アンケートを見ると、「みんなに体験してほしい」という意見が多く、実際、参加者の大半が友人・知人からのクチコミというのにも頷ける。
また、この、「五感のバランス」を取り戻す場をより多くの人に体験してもらいたいという思いと、視覚障害者の安定した雇用機会を確保しようとという狙いから、DID日本常設準備委員会を設置。既に、全盲を条件としたアテンドバンクも設立され、DIDの運営に関わるライセンスを交付したところだという。現在登録者は約30人、うち10数人が今回のアテンドとして関わった。3年前からアテンドを務める木下さんは「DIDに関わることで、自分たちが普段何気なく生活していることに、もう少し胸をはっていいのかなと思えるような、気持ちの切り替えがありました。今後もできる限り手伝いをしていきたいと思います」と話す。
「このプロジェクトには、高齢化社会のデザインやこれからの世の中の仕組みへのヒントが隠されているのではないでしょうか。今後、常設展示が実現しても消費される『商品』ではなく、100年続くような社会の中の『仕組み』にするにはどうしたらいいか考えているところです」(金井さん)。
[取材・文/笠原桐子+『ACROSS』編集室]