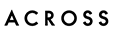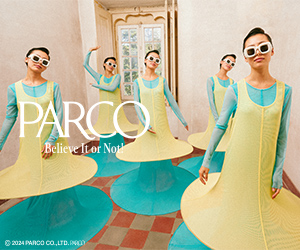11月初旬、今年も2つのデザインイベントが青山・外苑前で開催された。円いピンクのプラスティックバッグはデザイナーズウィーク、トリコロールカラーのトートバッグはデザインタイド。期間中、原宿表参道界隈では、それそれの会場で配られた公式バックを持つ若者たちで賑わった。
Design Tide in Tokyo 2006/デザインタイド
11月1日〜5日に開催された、今年初めてメイン会場を設けた「デザインタイド2006」は、独立系のデザイナーの作品を中心に、デザイナー同士のつながりも生むという趣旨で昨年より始まったデザインイベント。もともとIDEEの黒崎元代表が企画・運営していた「東京デザイナーズブロック(TDB)」を受け継いだもので、その特徴でもあった、活動に賛同するギャラリーやショップなどのスペースを利用し、点在する小会場(エクステンション)を回遊するような「街」との一体感も健在。明治通り沿いにある取り壊しが予定されているビルのメイン会場の他、青山界隈に約30もの小会場が設けられ、地図を片手にオリエンテーリングさながらのカップルや親子連れで賑わっていた。
今回のテーマは「Design&Peace」。そのコンセプトの企画展ともなった、ゴミを再生し作品にしようというアートプロジェクト「treasured trash(=タカラモノニナッタゴミ)」には、オリジナルの資源ポスト(ごみ箱)や、ペットボトル、使い古したスニーカーを用いたオブジェなど、さまざまな分野で活躍するデザイナーやアーティストの作品が目を引いた。その他にも、メイン会場のビルの1階と3階には、国内外60組以上のデザイナーによるオリジナル作品が展示され、1階の奥には、物販スペース「Tide Market」も。
「すごく刺激を受けました。モノ作りはまず製作者が楽しまないといけない、という基本的なことに気づかされました。私も帰って頑張ります!」(29歳・女性・染織デザイナー)
「斬新なアイデアがいっぱい。商品化してほしいものも多いですね」(26歳・女性・インテリアデザイナー)
「見るだけではなく、実際に買えるのがいいですね」(35歳・編集者)
また、11月3日には、「デザインで人と人がつながる」という「デザインタイド」を象徴するパーティ企画として、デザインユニット「クライン・ダイサム・アーキテクツ」がホスト役を務めたトークイベント「ぺちゃくちゃないと」が開催。20枚のスライドを20秒毎に投影しながら、クリエーターが自ら作品の解説やデザインへの想いをプレゼンテーションするというもので、ふだん、なかなかきちんと読むことの少ない作品についての解説を、作家自らがそれぞれの言葉で語ってくれることで、訪れた人それぞれの解釈の差異に気づかされたり、作品への熱い想いを通して新たな発見をするなど、新鮮な企画となっていた。
ちなみに、海外から来日したアーティストが話す英語に対して、司会者が通訳するはずのところ、「だいたいみんなわかるよね」というユルい雰囲気。たしかにその場に集まっていた観客の多くは、“時差”なくユルく頷いていたのだが。協賛のビールメーカーからは新作ビールも振舞われ、会場は終始和やかな感じに。
「デザインを通じて、お金をかけずに、人やモノに『つながり』を持たせたい、というのが東京デザイナーズブロック(TDB)以来貫いているコンセプトです。ショップやギャラリーといっしょに取り組むことで、街とのつながりも持つことができ、さらに、そこに企業が独立系のデザイナーたちがコラボするなど、ここでの出会いから新しいものが生まれることにも期待しています」と言うのは実行委員長の青木昭夫さん(28)。
「スローガンに掲げた『ほんとに必要なものだけを』とは、『モノを作ることは破壊することが前提』というジレンマを感じていたからなんです」と青木さんは話す。
実は、当初は青山の国連大学中庭をメイン会場に使うつもりだったそうだが、専用のテントを建てた場合、会期終了後にはそれらがゴミになる、ということで急きょ、近々取り壊しが決まっている明治通り沿いのビルに変更したのだそうだ。使われたイスやテーブルも中古品。舞台装置で使われた木材を仕切りとして使うなど、リサイクルにこだわった。
「委員会として新たに作ったものは公式ガムテープだけです。廃棄物をガムテープでまとめて『つないでいった』というわけです(笑)。今回メイン会場を設けたことで、みんなが集まれる場所ができ、そこに行けば誰かに会える。それがネットワークになり、デザイナー同士の環も広がったのでは」(青木さん)。
イベントには渋谷区長も来場しており、今後は行政とのコラボレーションも計画中だとか。
「デザインには人々の日常の暮らしを豊かする力があるんですが、日本ではまだそのことがあまり認知されていません。そういう意味でも、デザインはもっと社会に還元をしていくべきだと思います。欧米では、公共の建物の設計段階でデザイン費を約10%組み込んだりしているんですよ」(青木さん)。

若者に人気のトラックの幌を再利用した
バッグブランド「フライタグ」の実演
販売コーナー
バッグブランド「フライタグ」の実演
販売コーナー

古くなったスケートボードを材料にして
いるアクセサリーデザイナー2人組
いるアクセサリーデザイナー2人組

特殊なプログラムにより突然ツノのような
ものが出たりヘンなツメが生えたりする影
絵のインスタレーション「シャドウモンス
ター」
ものが出たりヘンなツメが生えたりする影
絵のインスタレーション「シャドウモンス
ター」

特殊な塗料により外気温によって色が変化
する人形「SWMO」。この塗料を日常生活で
活かすアイデアを募集だとか。
する人形「SWMO」。この塗料を日常生活で
活かすアイデアを募集だとか。

会場ではスターバックスのコーヒーが
無料で配布されていた
無料で配布されていた

テントのなかにはカフェコーナーも

すっかり定番になったコンテナ展示。
ひときわ目立ったナイキのブース
ひときわ目立ったナイキのブース

望遠鏡のような筒を覗くことで「LOVE」を
確認する作品を展示したものづくり大学の
学生2人組
確認する作品を展示したものづくり大学の
学生2人組

TOKYO DESIGNER'S WEEK/デザイナーズウィーク
「デザイナーズウィーク2006」は、今から21年前の1985年に始まった日本最大のデザインイベントである。当初はいくつかのインテリアショップなどを会場として開催してきたが、05年より神宮外苑の広場に中央会場を設定。今年も、全長165メートルの特設テントやコンテナを並べたブースなどをメイン会場に、10月31日から11月5日までの6日間開催。約7万4,870人もの来場者で賑わった。
今回のテーマは「LOVE」。森ビルや三井不動産、東京電力、コクヨ、バルス、月刊ソトコト、アドビシステムズといった企業がサポートメンバーとして参画している他、ナイキやパイオニア、ダイキン、TOTOなど、審査を経た国内外約150以上の大手メーカーやデザイナーが出展。一方、中庭には、国内外からスペースデザインや美術系の大学生、専門学校生の計47校、約500点もの作品を集めた「学生作品展」のコーナーもなど、企業、インディペンデントのデザイナー、学生とトレードショーらしい構成となっていた。
さらに、05年からは、ロンドンを本拠地とするインテリア見本市「100%デザイン」と提携し、その「東京版」として「100%デザイン東京」も同時開催に。いくつか分散して開催されているイベントのなかでも最も多くの人で賑わっていた印象を受けた。
「毎年来ていますが、いつも新鮮なデザインと出会えてとても刺激になります。まだ来たことがない人には一見の価値アリだと言いたいですね」(24歳・女性・デジハリの学生)
「今回初めて来たんですが、会場が大きくて驚きました。ひとつひとつのブースが見応えがあるので、予想以上に楽しんでいます。もっと早い時間に来れば良かったなあ」(22歳・男性・webデザイナー)
同イベントを主催するNPO法人デザインアソシエーションの代表、川崎健二氏は、「将来的には、ファッションや食なども含めた『東京デザインスタイル』が見える形にしていきたい。デザイナーと地場産業を結びつけ、行政やメディアを含め、新しい日本の産業作りにつながれば」と何かのインタビュー記事で語っていたように、夢はまだまだ壮大のようだ。
デザインタイドとデザイナーズウィーク。いずれも、展示されている作品に触れたり、解説を聞いたり、イベントに参加して楽しむだけでなく、「買える」「持ち帰れる」という、消費の要素が入っている点が新しい。
これまでの見本市のような「業界関係者向け」という枠を越え、「一般消費者向け」の万博的なアトラクション要素や店舗(ショップ)のような小売り要素を加えたことで、かえって「デザインを啓蒙する」というイベントの主目的が、人々に、また社会に浸透していくのでは。情報の発信者と受信者が限りなく近づいている現代ならではの新しい見本市の形といえそうだ。
[取材/写真:福田健一(フリーライター)+『WEBアクロス』編集室]
今回のテーマは「LOVE」。森ビルや三井不動産、東京電力、コクヨ、バルス、月刊ソトコト、アドビシステムズといった企業がサポートメンバーとして参画している他、ナイキやパイオニア、ダイキン、TOTOなど、審査を経た国内外約150以上の大手メーカーやデザイナーが出展。一方、中庭には、国内外からスペースデザインや美術系の大学生、専門学校生の計47校、約500点もの作品を集めた「学生作品展」のコーナーもなど、企業、インディペンデントのデザイナー、学生とトレードショーらしい構成となっていた。
さらに、05年からは、ロンドンを本拠地とするインテリア見本市「100%デザイン」と提携し、その「東京版」として「100%デザイン東京」も同時開催に。いくつか分散して開催されているイベントのなかでも最も多くの人で賑わっていた印象を受けた。
「毎年来ていますが、いつも新鮮なデザインと出会えてとても刺激になります。まだ来たことがない人には一見の価値アリだと言いたいですね」(24歳・女性・デジハリの学生)
「今回初めて来たんですが、会場が大きくて驚きました。ひとつひとつのブースが見応えがあるので、予想以上に楽しんでいます。もっと早い時間に来れば良かったなあ」(22歳・男性・webデザイナー)
同イベントを主催するNPO法人デザインアソシエーションの代表、川崎健二氏は、「将来的には、ファッションや食なども含めた『東京デザインスタイル』が見える形にしていきたい。デザイナーと地場産業を結びつけ、行政やメディアを含め、新しい日本の産業作りにつながれば」と何かのインタビュー記事で語っていたように、夢はまだまだ壮大のようだ。
デザインタイドとデザイナーズウィーク。いずれも、展示されている作品に触れたり、解説を聞いたり、イベントに参加して楽しむだけでなく、「買える」「持ち帰れる」という、消費の要素が入っている点が新しい。
これまでの見本市のような「業界関係者向け」という枠を越え、「一般消費者向け」の万博的なアトラクション要素や店舗(ショップ)のような小売り要素を加えたことで、かえって「デザインを啓蒙する」というイベントの主目的が、人々に、また社会に浸透していくのでは。情報の発信者と受信者が限りなく近づいている現代ならではの新しい見本市の形といえそうだ。
[取材/写真:福田健一(フリーライター)+『WEBアクロス』編集室]