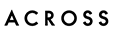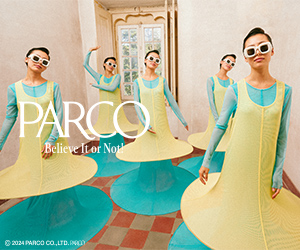原宿駅から歩いて10分弱、アパレルメーカーやデザイン会社が集まる渋谷区千駄ヶ谷の一角に、紙に関連する雑貨・ステーショナリー販売と活版印刷のオーダーを受け付けるショップ「PAPIER LABO.(パピエラボ)」が、07年6月2日オープンした。
活版印刷とは、活字を組み合わせた版で印刷する昔ながらの印刷方法。印刷のデジタル化により今や失われつつある技術であるが、職人による手作業ならではアナログな質感が、最近デザイナーなどクリエイターの間で見直されているという。同店は、そんな活版を通して出会った若きクリエイター、江藤公昭さん(29歳)、高田唯さん(26歳)、武井実子さん(31歳)の3人が生み出したショップである。
運営するのは、家具・雑貨の製造販売と住宅や店舗の設計施工などを行い、千駄ヶ谷周辺にも家具店やカフェなどを展開する有限会社ランドスケーププロダクツ。店舗は、同社の工房的なスペースを社内でリノベーションしたものである。
ショップを立ち上げた3人はそれぞれに本業を持つ。高田さんは「allright graphics(オールライトグラフィックス)」を主催するグラフィックデザイナー、武井さんは自らのブランド「sub letter press(サブレタープレス)」で活版印刷のポストカードなどを製作する傍ら、外部ディレクターというスタンスで同店を立ち上げた。そして、3人の中心的な存在としてショップに常駐しているのが、ランドスケーププロダクツのデザイナーでもある江藤さんだ。
「仕事で海外に買い付けに行った際に、へこんだり擦れたり、にじんだりしている質感がいいなと思って集めていた印刷物が活版印刷だと気づいてからは、集中してコレクションしていたんです。僕と社長の間では以前から、活版印刷がいいねという流れがあったので、今回の企画を提案したときもスムーズに受け入れてもらえたんです」(江藤さん)。
コンセプトは“紙と紙にまつわるプロダクト”。国内外を問わず、質感にこだわったステーショナリーや雑貨などの商品を取り扱う。「postalco(ポスタルコ)」のノート(840円〜)、大阪の「itohen」のレターセット(525円)、「makoo」のメモノート(357円)、高田さんによる「オールライト工房」のカレンダー(1ピース210円)や、武井さんの「sub letter press」のポストカード(189円〜)などに加え、オリジナルの鉛筆削り(1,470円)や、アート本などの商品を、大きく“紙から波及する物”としてとらえて表現しているという。人気商品は、鹿児島の職人にオーダーする薩摩柘植の印鑑(片面6,300円、両面12,600円)だそうだ。
「活版が好きな人が共通して持っている、言葉にできないけど共有できる感覚というものがあると思うんです。ですから、企画書なんかを作らなくても感覚的に、方向性や扱いたい商品をすぐに分かり合えていました」(江藤さん)。
そもそも3人の出会いは、今年5月に三軒茶屋の世田谷文化生活情報センター「生活工房」で開催された「活版再生展」に関わったことだった。「生活工房」の竹田由美さんが、紙にまつわる大平一枝さんの著書『かみさま』に触発されて企画した同展では、江藤さん率いるランドスケーププロダクツが空間構成などを担当。高田さんはフライヤーやカタログと内部のグラフィックなどのアートディレクションを、武井さんは企画協力をそれぞれ行った。「不思議な力で、今まで会うはずのなかった人々に次々と出会った」と江藤さんは言う。
「3人で話しているとすごく話が合ったんです。活版好きというだけでなく、音楽やファッションの感覚も含めて、同じ流れの中にいるのだろうなと。Macで言うとOSが一緒、みたいな時代の感覚があるんだと思います」(江藤さん)。
同店の最大の特徴は、実際に活版印刷での印刷物をオーダーできること。名刺やショップカード(片面200枚21,000円〜)、はがき(片面200枚27,300円〜)の他、カード類や招待状などの相談も可能だ。制作は、活版に魅せられたメンバーのひとりである高田さんとその兄である素文さんが「オールライト工房」という活動名で、銀座や三軒茶屋に残る活版印刷所で職人さんの協力を得て技術を受け継ぎながら行っている。高田さんらは「活版再生展」で展示された機材や活字一式を全て譲り受けており、来年には大田区で実際に活版印刷所「オールライト工房」を開き、活版の新たな可能性をさぐっていく予定だ。
「活版印刷を残していこう、というのが活版再生展の命題でもありました。オープンは来年を予定していますが、都心から少し離れた場所になるので、近場でお客さんと工房をつなぐ窓口となるショップの必要性があったんです。新しい活版印刷所は今までにない開けたかっこいい空間を目指し、ゆくゆくはワークショップを開いたり、活版を通して人が集まるスペースにしたいと考えています」(江藤さん)
客層は、紙や手紙が好きな20〜50代までと幅広く、全体の8割が女性。取材中にも、どこからともなく次々と女性客のグループが訪れ真剣に雑貨類を選んだり、名刺や印鑑の相談をする男性客の姿もみられた。名刺は平均1日1人、多い時は5人以上の発注を受けるそうだ。印刷物の発注をするのは、アーティストをはじめとした、感性を重視する人が多いとか。
活版印刷に興味はあっても、今でも残る街の小さな活版印刷屋は素人には敷居が高く、発注の仕方や価格など不安な点も多い。それを、雑貨や文具なども扱うショップでオーダーできることで、容易に活版に触れられる機会を与えられればいいと江藤さんたちは考えている。活版印刷をブームにしたいのではなく、活版印刷と消費者を繋ぐ役割を担うショップというスタンスだ。新たな切り口で昔の技術を再生し新しく育てていきたいという江藤さんたちの思いが、今後どのようなかたちで表現され印刷物として世の中に広まっていくのか。今後の活動に注目したい。
[取材・文/笠原桐子+『WEBアクロス』編集室]

店に常駐する江藤さんが、オールライト
工房の窓口として活版印刷のオーダーや
相談を受けてくれる。
工房の窓口として活版印刷のオーダーや
相談を受けてくれる。

ノートひとつとっても個性豊かなセレクト。
実際に手にとって触れることでさらに
その個性が感じられる。
実際に手にとって触れることでさらに
その個性が感じられる。

武井さんの「sub letter press」の
ポストカードは、もちろん活版印刷。
あたたかみのある独特の世界観が魅力。
ポストカードは、もちろん活版印刷。
あたたかみのある独特の世界観が魅力。

活版で数字のプレスだけをした
「allright graphics」の万年カレンダー。
自分で数字を書き込んで使用する。
「allright graphics」の万年カレンダー。
自分で数字を書き込んで使用する。

一番の人気商品だという薩摩柘植の印鑑は、
結婚や起業といった人生の節目にオーダー
する人が多いのだそう。
結婚や起業といった人生の節目にオーダー
する人が多いのだそう。

同店オリジナルの鉛筆削り
「ペンシルヴィラ」。こう見えて
シャープナー部分にステッドラー社製を
使用している本格派。
「ペンシルヴィラ」。こう見えて
シャープナー部分にステッドラー社製を
使用している本格派。