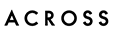怒涛の新書ラッシュのなか、理系ジャンルのものも多いが、ひとつ頭を抜けた感のある本書である。「○○力」「〜のウソ」「〜する人、しない人」、9割とか、%とか、扇情的なタイトルの中にあって、本書はどこか静かだ。ただ、見たときから、ふしぎな存在感があった。生物と無生物の「あいだ」。ひらがなである。なにか好きなにおいがして読み始めたら、プロローグの数行でレジ直行決定、の本であった。冒頭を抜粋しよう。
私は今、多摩川にほど近い場所に住んでいて、よく水辺を散策する。川面を吹き渡ってくる風を心地よく感じながら、陽光の反射をかわして水の中を覗き込むと、そこには実にさまざまな生命が息づいていることを知る。
この散文に続き、人は生物と無生物の何を見分けているのか、そもそも生命とは何か、という問いが続いていくのである。文系の人も、これでがっちりつかまれるのではないだろうか。
本書は、分子生物学者の著者が、アメリカにわたり博士研究員(ポスドク)として細胞内タンパク質に関する研究した経験と、DNAの二重らせん構造発見を中心とする分子生物学の歴史を通して、「生命とは何か」という根源的な問いを追求した本である。と、断言していいものか、何しろ文系人なので、科学ものにはつい及び腰になりがちだが、ともかくそのように読んだ。
二重らせんといえば世紀の大発見で、一時期ブームともいえるくらいよく目にしていた気がする。DNA、核酸塩基配列、メセンジャーRNA、一般人にも懐かしい教養だ。そこからさらに分子生物学が追求しているものについて、本書は語っている。
原子にくらべわれわれの身体がこれほど大きい理由、生き続けるための唯一の方法は負のエントロピー(=秩序)を取り入れる(=食べる)こと、など発見感あふれる記述が続くのだが、いちばんの衝撃はやはりこれだろう。
生命とは動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)にある流れである
生命は、流れ? 「肉体というものについて、私たちは自らの感覚として、外界と隔てられた個物としての実態があるようにかんじている」が、私たち生命体は、分子のゆるい「淀み」でしかない、という。しばらくぶりに会って「お変わりなく」という挨拶をかわすけれど、分子のレベルでは人はすっかり入れ替わっているので、「お変わりありまくり」だとか。身体について、こういう言われ方をしたのは、初めてである、たぶん。もちろん著者の研究を元にしての結論なのだろうから、反論も(特に同業者や理系の人から)あるのだろうが、これを読み、この視点に出会えたのは、私は収穫だった。
後半は、著者が属するチームの、細胞内たんぱく質の研究についての試行錯誤や、論文発表をめざす競争、ラストにまたあらたな発見がドラマチックに描かれている。ほかにもロックフェラー大学での野口英世の(偉人としてではない)痕跡、DNA解明の際の科学者たちの政治や競争など分子生物学史の裏側、著者のポスドク暮らしやニューヨーク、ボストンの街の様子など、よみどころが多い。海辺の貝殻や、海の精霊などが現れる章の導入部も、味わい深い。
このかんじ、思えばこれまで何度か味わってきているな、と思い出す。子ども時代の「ファーブル昆虫記」、宇宙ブームの頃の「COSMOS」。大人になっても、遺伝子とか、脳とか、ときどき読む「科学よみもの」は、なかなかに新鮮で、幸せな体験だ。その真偽や実用度以上に、センス・オブ・ワンダーは人生に必要なものなのだろうと思う。
[神谷巻尾(フリーエディター)]
しあわせな科学よみもの
読みたくなった本 + 思い出した本
▪読みたくなった本
・『プリオン説はほんとうか?』福岡伸一(講談社ブルーバックス)
・『生命とは何か』E.シュレーディンガー(岩波新書)
・『二重らせん』ジェームス・D・ワトソン(講談社文庫)
・『探偵ガリレオ』東野圭吾(文春文庫)
▪思い出した本
・『ファーブル昆虫記』J・H・ファーブル(集英社など)
・『COSMOS』カール・セーガン(絶版?)
・『ホーキング、宇宙を語る』ステイーヴン・W・ホーキング(ハヤカワ文庫)
・『そんなバカな!』竹内久美子(文春文庫)
・『脳とクオリア』茂木健一郎(日経サイエンス)