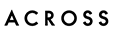渋谷駅前のスクランブル交差点を右に曲がり、JR山手線に沿うように原宿方面へ歩いていくと、明治通りにつながるガードをくぐる手前、渋谷消防署方面に左方向に緩やかな坂道がある。1964年の東京オリンピックが開催され人通りが少ない、ちょっと地味な通りだった。
しかし、1973年に渋谷パルコ パート1がオープン、パルコ前の「区役所通り」と呼ばれていた坂道が「公園通り」と名づけられ、この消防署前の坂道界隈は、「ファイヤー通り」と名付けられ、ちょっとざわめきはじめたのだった。
そして1974年、消防署の向かいに1軒のヘンな店がオープンした。店の名は「文化屋雑貨店」。医者の家に生まれながらも美大に進み、デザイン事務所に勤めていた長谷川義太郎さんが店主となって、独自のセンスで集めたアンティークや道具、ガラクタ類を販売。それらの品々は新しい概念としての「雑貨」となって若者たちの心をつかみ、文化屋雑貨店は瞬く間に日本のカルチャーシーンの台風の目となっていったのだった。



そんな渋谷の中でもさらにマイナーな場所に店を構えることになった長谷川さん。長谷川さんの“街センサー“は、果たしてどう動いたのだろうか?
「デザイン事務所に勤めてる時代から、下町を歩き回って『金太郎の腹掛け』とか『きいちのぬりえ』とか自分が面白いと思うもの、欲しいものを買ってきては事務所のデスク周りに貼ったり飾ったりしていわば個人展覧会をやってたんです。そうしたらそれを面白がったり欲しい人が出てきましてね。なんというかな、だんだんだんだん自分が“雑貨“をやっていこうという気持ちになってきた。グラフィックデザインを続けることに行き詰まりを感じて放り投げた時に、お店をやることによって自分の、評価っていうのはおかしいけれど、自分の考えることがどれぐらい世の中に浸透していくかってことを試してみたくなっちゃったんです。だから長くやろうとかそういう気は全然なかったんです。でもね、店をやろうと思ってから1年ぐらいは場所を探していたんです」(長谷川さん)。
その後、自由が丘とか横浜の中華街とかに足を延ばしたりしながら、渋谷周辺をずっとぐるっと回って、ほとんど毎日のように不動産さんを巡ったと話す。
「渋谷消防署の辺りについては、不動産屋のオヤジがやめなさいって言うの(笑)。あの辺りって本当に何もなかったから。鉄道関係やガス会社なんかの倉庫があるような通りだったんですね。でも渋谷と原宿間をクルマで通り抜ける道になるな、と勘が働いたんですよ。明治通りが混んでる時に必ずあそこはプロの運転手とかが通り抜けていたわけです。この場所は立地としてすごくいいんじゃないかなと思ったんです。雑誌のスタイリストが車で乗り付けるようなイメージですね。家賃が安かったのもある。当時から意外と計算高かったんです(笑)」(長谷川さん)。

「文化屋雑貨店は1974年のオープンですが、私は1972年からビギに勤めていたんです。当時ビギに太郎さん(長谷川さん)の悪友の小栗壮介さんがいて、”僕の友人が店を始めたから来てよ”って言われて行ったのが最初です。彼は太郎さんと全然違う小洒落た男で。アスコットタイするようなタイプでした(笑)。彼が関係するならあんまりピンとこないなーなんて思いながら行ってみたら、全然違う! 何ここスゴイ!ってなった(笑)。それから文化屋に日参するようになりました!」。

「小栗壮介と僕は麹町中学の同級生だったんです。もう1人同級生に水野誠一という男がいて、後に西武百貨店社長になって、渋谷ではロフトやシードを手がけました。その小栗が代官山のビギのオフィスの部屋を給料日の晩に貸してあげるから、いっぺんお前の集めた品物を持って来いよって言うんです。デザイナーの稲葉賀恵さんも来てくれて、僕がクルマいっぱいに持って行ったものを買ってくれたの。それが文化屋始めるちょっと前の話です。実
家の病院を閉めるときもベッドや医療器具、ナースシューズとかバザーしてすでに感触は持ってたんですが、ビギでそんなに売れちゃうの!ってさらに自信を持ちましたね」と長谷川さん。
「当時ビギは代官山のヒルサイドテラスにあって私、横森もそこにいました。その頃のファッション業界は、変なやつばっかりだったのね。社会的な認知度がなかったから、アングラな感じで。訳のわかんない連中が変な格好してうろついてたわけです。まだそんなにおしゃれっていうことが認められてなかった時代です。マンションメーカーっていわれたりしましたが、社会的認知度はなかったけど、私たちにはセンサーだけはあったの。面白いものに飛びつきたいっていう人たちの塊だったのね。だから太郎さんの持って行ったものをみんな買っちゃった。私は実はその日出社してなくて本当に残念だったわ!」(横森さん)。
「ぬりえの蔦谷喜一さんについて話すと、グラフィクデザイナーして時に築地の駄菓子屋とか覗いていると足元に喜一さんのぬりえが袋に入って無造作に置いてあったんですよ。それを買ってきて、事務所で1人で喜一展を開いたりしてたんです。そうしたら、ある日、ボスの菊池信義さんが「おい、喜一さん生きてるかな? お前探してみろ」って言われて。問屋街に行ったりいろんなところ聞いて回って喜一さんに行き着いたんです。お金持ちの似顔絵なんかを描いて生きていた。塗り絵はもう全然ダメだと、テレビの時代だと。もうこんなに古いものがいいわけないと、あなたたちがここにきたのは怪しいとか言われて(笑)」(長谷川さん)。
その後、『アンアン』に掲載されるとものすごい反響に。
「だんだん喜一さんも『あなたの言ってることは嘘ではなかった』と絵を描き始めてくれて、銀座の資生堂ギャラリーが展覧会やってくれたの。そしたらおばあさんが病院から出てきて見に来て、おばあさんが言うには戦争の時にみかん箱にこの喜一さんのぬりえを詰めて疎開したり逃げたとかね。それまで誰も見たことがない喜一さんを銀座で見られるってことで、とうとうNHKまで取材に来た。喜一さんも驚いて本当にこんなことになるなんてと。その後本も出たりしましたけど、何とタイムカプセルにぬりえが入れられて20世紀の文化遺産になったりもしました(笑)。時代のウラ通りを動いてきたものを、オモテの文化に出してきた時に評価されるのかどうかってのは、文化屋がやってきたことと同じなんです。つまり、倉庫に眠っていたランプシェードが実際にオモテに出してきた時に売れるかどうかってのが僕にとって命題だったんです。それが動いていくわけです、どんどんどんどん。喜一さんだって、ひょっとしたら多くの人に知られないまま亡くなって、世の中からいなくなっていたかもしれないんです。それが、93歳まで文化屋の絵を描いてくれた。多くの人が評価してくれたからです」(長谷川さん)。
「やっぱりそこまで持ってくのがすごいですよね!」と横森さん。
「それはある意味で結果なんです。もっと早くやっていれば喜一さんにもっとお金が入ったはずで、それは申し訳なかったんですが、でも歴史の中に蔦谷喜一ってのが残ったことに関してはしてやったりとは思いましたね。そうそう、文化屋は陶器の業界にでも評価されてるんですよ。問屋街に行くと文化屋さんに表彰状出したいって言われることがあるくらい(笑)。本当に潰れかかった店ばかりだったもの」(長谷川さん)。
その後、雑貨市場はグローバル化し、今や海外でもZAKKAで通用するまでになっていった。ホーローもブリキ製品もおしゃれなセレクトショップで扱われたり、洗練されたライフスタイル誌の誌面を飾っている。文化屋雑貨店に続けとばかり大中や宇宙百貨も賑わいを見せ、その後はロフト、ヴィレッジヴァンガード、100円均一ショップなど、様々なスタイルの雑貨ショップが生まれたが、元々はこの文化屋雑貨店が発火点なのである。
「僕にとっては大中やヴィレヴァンも敵ではなかったね。僕がインスパイアしたものでみんなが動いているわけだからね」。
長谷川さんは店がブレイクしても相変わらずインディーズ魂に溢れたパンクな下町っ子で、権威の押しつけが何より嫌い。その魅力もあってか、文化屋雑貨店にはスタッフから客まで多種多様な人々が集まって、常に店から道路に人がはみ出るほどごった返した。
「僕らが発信の材料を出して、店に来た人たちが膨らませたり拡大していったのでしょうね。ポール・スミスだってそう。僕たちが作った靴下やポット、カメラをプリントしたポーチなんかをロンドンのショップで売らせて欲しいと。それで10年ぐらい延々と何100個とか売ってましたね。
ある時はアンディ・ウォーホールがやって来て2時間ぐらい店内を見てたけど、日光写真の原版1枚買ってきました(笑)。イギリスのデザイン集団トマトのカール・ハイドはインドの’70~80年代の教科書代わりの教育用ポスターをすごく喜んでね、何10本も買って行きましたよ。他にも、文化屋オリジナルの灰皿にローマ法王をプリントしたこともあって、それがイタリア人に受けた受けた(笑)。文化屋は宗教とかも全部超えてやってましたから。いろんな枠を取り払って自由でしたからね。
一方、スタッフでは店のアルバイトのなっちゃん(島崎夏美)が今でいうカリスマ店員みたいにブレイクして、『アンアン』のモデルになったり。そんな彼女に憧れたデビュー前のキョンキョン(小泉今日子)が通ってきたり。
バイトだった佐藤チカちゃんが立花ハジメ君や横森さん巻き込んでテクノバンド「プラスチックス」ができたりも。沼田元氣君もバイトしてました。まあボーダーレスにいろんな人が出入りして賑わってるうちに、文化屋前の通りをファイアー通りというようになって、僕はそれがとても嫌でね。あれはポパイの取材でライターがつけたのだったかな。おかず横丁とか自然発生的な通り名ならいいけど、スペイン坂とかファイアー通りとか、通りのネーミングが僕には何だか上から目線に思えてね。当時、ファイアー通りについての取材は全部拒否しましたよ(笑)」。
その後、ファイアー通りは今では標識が作られるほど定着。ストリートのネーミングは現在も街づくりの定法となっている。一方、文化屋雑貨店はキッチュな絵柄の靴下などオリジナル商品の爆発的ヒットで、中国や香港などへの買い付けや、全国の支店との連携、さらに大手商業施設や海外からも出店の声がかかるなど、メディア露出も含め、多忙を極めていった。
「ある概念を出せばあとはプロたちが、やっていくわけですよ。そのきっかけみたいのを出すのが文化屋をやってて一番面白かった。“雑貨=zakka”という概念をみんながどんどん認識してくれて。それは強烈でしたね。
おそらく渋谷にお店を出したおかげだと思うんです。渋谷にあったから外国人だって、例えばカール・ハイドだって原宿ラフォーレから歩いてきたりできるわけです。当時はこれが下町にあったら彼ら行かなかったかも。そういう渋谷ってものを最初につかまえたから、その先どんどん世界まで広がっちゃったと思うんです。店自体は本当にボロい店なんだけど、内装も自分たちでやってたし全然金がかかっていない。金のかかんないことが一番面白いって(笑)。金がかかるとだんだんつまらないこともやらなきゃなくなる。それでも年商は億単位になってましたね。1個100円もしないヘアピンが爆発的な売り上げで稼いでいくわけですから、それはそれでクタクタにはなりますよ。そのうち何事もフォローすることばかりで、なんだかばかばかしくなってきた頃に地上げの話がきたんです」(長谷川さん)。
借店舗だったがビルの建て替えのための立ち退きだったという。時はバブルの真っ盛り。億単位の年商額を軽く越える立退料をもらって、文化屋雑貨店は1988年、原宿に移転した。もちろん移転先でもその勢いは衰えず、後にその場所もキャットストリート、裏原宿として若者カルチャーの中心地になっていった。
「今でいうMD力とか、けっこう総花的に太郎さんの才能そろっていますよね。先を読む力もあるし。商才もあるし」と言う横森さん。「それでお金にならないってすごいよね」と長谷川さんは笑う。
「いえいえ、太郎さんの感覚はすごい素直っていうか正直。だから、儲かることになっているんだとも思いますけどね(笑)。でもなによりも、太郎さんの“人生遊んでるっ!”て感じがいちばんです!」(横森さん)。

先日、清澄白河でトートバッグ中心のポップアップショップを開いた時には、後に芥川賞作家となった滝口悠生君と出会いました。またセクシーキラーっていう面白い奴がいて、金太郎の格好してたり。でも体臭が臭いんですよ(笑)。彼が手伝ってくれて、一昨年は神田で「第1回文化屋雑貨点」という展覧会を開き、みんなが文化屋で売りたいモノを持ち寄って販売会しました。
今神保町に「鶴谷洋服店」ってのがあって、そこに商品置いて文化屋雑貨店の看板も出してます。その2階を勝手に事務所代わりに使ってます(笑)。
最近は一橋大学の松井剛先生が“グローバルなZAKKA”を研究調査していて文化屋雑貨店に行き着き、特別講義を頼まれたので1人じゃ面白くないから僕の関係者を20人ぐらい引き連れて行きました。そしたらゼミの学生より多くなっちゃった(笑)。
とにかくすごい才能を持ってる人たちをオモテに出したい気持ちは変わらないですね。今の僕にとっては雑貨=人間なんです。そうした人たちがどんどん伸びていくのは一番面白い、僕が伸びれば一番面白いのにこれが伸びないんだな(笑)」といつまでも話がつきず、トークイベントの時間を大幅に過ぎてもまだ、“雑談”が続いた。
現在、文化屋雑貨店は、世界で唯一、香港にお店があるという。実は、東京の文化服装学院を卒業した香港からの留学生があまりに文化屋雑貨店が好きすぎて、その熱意から、特別に長谷川さんが「香港文化屋雑貨店(youtu.be/IaRZ7L78g54)」としてお店をオープンすることを許可したのだという。
時代・社会が代わっても、国や文化、世代を越えて“文化屋雑貨店”の新しいネットワークが広がっているようだ。
[文/立石和浩(エディター、ライター、プランナー)]