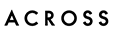新型コロナウイルス(COVID-19)禍で、メディアの効率化・デジタル化が求められ、またオンライン上でコンテンツを提供するサービスの普及は一気に加速した。エンタテイメントやアートの分野でも顕著で、コンテンツの無償公開、ストリーミングサービスやライブ配信、VRなど今なお広がり続けている。
過去に同じく“デジタル化”が加速したのが「電子書籍元年」と言われる2010年以降。タブレット端末などデジタルツールの進化により、紙の本の存在意義が問われることとなった。そしてその後の2011年の東日本大震災直後には様々なデジタル化されたコンテンツが 無償提供されるなど、出版業界でも電子化への取組が広がった。
こうした近年の“デジタル化”の一方で、よりパーソナルなもの、アナログなもの、質感や素材感の感じられるものが好まれる動きもじわじわと増え続けている。今回取り上げたのはテキストや編集、印刷、製本など、本が持つ様々な要素をアートとして昇華する「ブックアート」。特定の文章を読んでもらうことを目的にした本とは異なり、自由な発想やテーマ、 表現方法をもとに作られる美術作品だ。
そんな「ブックアート」を牽引しているのが、ブック・アーティストの太田泰友さん。
太田さんは、2017年に本場ドイツで史上2人目(日本人では初)となる現代ブックアートの最高学位「マイスターシューラー号」を取得。日本へ帰国後、同年に拠点となるアトリエ 「OTAブックアート」をオープンさせた。国内外で自身の活動を続けながら、アトリエでのワークショップなどを企画し、2018年10月には「OTAブックラボ」第0期をスタートするなど、日本ではまだ認知度の低いブックアートを広めるべく、活動の幅を広げている。
そんな彼に、ブックアートの魅力や、新たな取り組みである「OTAブックラボ」への思いについて伺った。
明確な定義がないから面白い「ブックアート」

2020年3月、アトリエにて撮影。
そもそも、ブックアートとはどんな作品なのだろうか。
「実は、世界でもブックアートの明確な定義というのはきっちりと定まっていなくて、いろいろな解釈があるんです。例えばわかりやすくブックデザインと比較すると、ブックデザインの場合はテキストやビジュアルなど読者に伝えたいコンテンツが先にあって、それを届けるために適切なデザインをするというもの。それに対してブックアートは、コンテンツを適切に届けるというよりも、まずコンセプトがあって、それを本が持つ色々な要素を使って表現することが重要だと感じています」。

太田さんの作品「Frucht I(フルーツ 1)」。レモンという物体をそのまま本に移し替えるというコンセプトが表現されている。
例えば、2020年2月21日からの「ポーラミュージアム アネックス展 — 真正と発気 —」(新型コロナウイルス の影響で会期中に休館。中止となった期間分は2020年9月26日〜10月11日に延期予定)に展示されていた「Frucht I」という作品の側面三方にはそれぞれ、①レモンを購入した時の情報(いつ、どこのスーパーの何番レジで、いくらで買った等)、②レモンを辞書で引いた時に出てくる言葉(本を開いた1ページ目に「レモン」という言葉を辞書で引いた時の文章、側面にその中に出てくる「黄色」「酸っぱい」などを更に辞書で引いた言葉が書かれている)、③レモンを使ったレシピが書かれている。
しかしもちろん、太田さんはこの作品でレモンのレシピを伝えたいわけではない。レモンそのものを本に移し替えるためにそういう表現を使っている作品なのだと太田さんはいう。
さらにブックアートの定義について、次のように続ける。
「作家である僕たちにもそれぞれ解釈がありますし、学芸員の方々にもいろいろな解釈の仕方があって、どういう風に定義すればいいかというのは難しさがあります。ブックアートというより『本かどうか』の話になりますが、例えば、『綴じていたら本』というのは分かりやすい。でも箱に紙が何枚も入っていてそれをブックアートだという人もいます。その場合は『印刷された紙が複数積み上がっている』というところで本と捉えているのだろうし、人それぞれに『こうなってさえいれば本だ』という感覚がある。そこに表現の面白さが詰まっていると思うんです」。

木片でできた制作物。青色の幅を2mm程度塗り足すことで表紙の厚みを表現し、よりリアルに“本らしく”見える。
そう言って彼が見せてくれたのは、表面に色を塗り、「WOOK」という文字の箔押しがされた“木片”。
「これはただの木材に色を塗っただけのもの。でもこういう風に青いところがあって、側面を天金・白・白と塗ると、きっと多くの人が本に見えると思います。比率も、天地よりも厚さが薄い方が本に見えるとか。逆に紙を使ってすごい(変な)比率の作品を発表したこともありますが、それが本に見えるかというのも一つ重要なこと。『どんなものが本に見えるか?』は人それぞれなんです。そういう意味で、作品を通して『これも本でしょ?』と表現することもブックアートだという感覚があります」。
定義を狭めるというよりも広げながら、いろんな境界を探っていくことに興味があると話す太田さん。自身の制作でも、これまでブックアートの本随と言われてきたような作品だけではなく、「こういうのも本の新たな可能性と捉えても良いのでは」というものを意識的に作っているそうだ。
以下は「ポーラミュージアム アネックス展 — 真正と発気 — 」の際の太田さんのコメントだ。
“自分らしい本の作り方を意識し始めた頃に、ウィリアム・モリス『理想の書物』(筑摩書房、2006年)を読んで、本の世界に心酔した。「〈芸術〉の最も重要な産物でありかつ最も望まれるべきものは何かと問われたならば、私は〈美しい家〉と答えよう。さらに、その次に重要な産物、その次に望まれるべきものは何かと問われたならば、〈美しい書物〉と答えよう」(訳:川端康雄)モリスはこのように〈家〉と〈書物〉を並べた。
本と建築には共通点がある。本にまつわる名詞には、「扉」や「柱」と呼ばれるものがあり、動線をコントロールしながらレイアウトを作り込んでいく点もよく似ている。人間よりも小さく、手で持つことができるのが本で、人間よりも大きく、身体ごと入ることができるのが建築だ。人間と比べた時のサイズ感に違いがある。大きさは異なるが、共に宇宙だ。
2019年以降、私が制作するブックアートに、手に収まらないものが出てきている。”
(太田さんのブログ“「ポーラ ミュージアム アネックス展 2020」に寄せて”より引用)

2019年に制作された“Book-Composition 22—Atlas from 1896”。1つ1つ異なるデザインが施された本の背表紙(のように見える)に、ウィリアム・モリス『ケルムスコット・プレス設立趣意書』(1896年)から引用した、様々な単語や概念などが箔押しされている。

“Book Para-Site 4—Chair 1”, 2020
2019年より太田さんが発表し続けている「Book Para-Site」シリーズ。今回の新作は「家具に本が寄生している」という着想から作られている。

「ポーラミュージアム アネックス展 — 真正と発気 —」の展示より “Book Para-Site 9—Box”、“Book Para-Site 15—Vase”、“Book Para-Site 17—Cutlery”

「ポーラミュージアム アネックス展 — 真正と発気 —」の展示よりBook Para-Site 4—Chair 1
日本人の感覚に合っている?ブックアートの魅力とは

「本(に関わる仕事)で生きていく」と決めていた太田さんは2013年にドイツに渡り、ブルグ・ギービヒェンシュタイン芸術大学に入学した。ドイツで唯一「ブックアート科」が設置されている大学だ。当初は製本についてより深く学ぶことが目的だったが、教授の元で学び、作品を発表していくなかでブックアートの面白さや、仕事として続けていけるという実感を得られたのだそう。2014年のライプツィヒ・ブックフェア(2020年はコロナウイルスの影響で中止となった)で初めて作品を展示し、そこで自分の作品が売れたことが大きな転機となったという。
「日本でも、趣味で本を作っている人がいたり、クラフト的な立ち位置で製本したりして、作品を販売している人たちがいます。僕もドイツに行く前にそういう活動に挑戦してみたこともありました。僕がそこで得られた経験は、何百円、何千円の世界。一生懸命作ったものを買っていただけてすごく嬉しいし、楽しいのですが、それを生業にするなんてとてもじゃないけど考えられませんでした」。
「ドイツに渡って住んだ家の家賃が、計画していたよりも高くなってしまって、初めての展示の前に追い詰められた状況でした。アルバイトをして生き長らえるか、日本に帰国するか悩みながらもなんとか迎えた展示の初日に作品が売れたんです。それまでには想像もできなかった金額で、ブックアートとして作品が売れた。お金だけではなくて、作品への自分の手応え、周りの評価、展示での評判、すべてにしっくりきた感じがありました。こうして自分の作品に救われたから、これからも他でなんとかしようとせずに、ブックアートに向き合って生きていこうと決意できた明らかなタイミングでしたね」。
そして2017年には、日本人初となるブックアートのマイスターシューラー号(ドイツの最高学位)を取得した。
その後、同年に彼は帰国。活動の拠点を日本に移している。
とはいえ、日本はブックアートに触れられる機会が少なく、認知度も低いのが現状。ブックアートを専門とする教育機関がなく、作家が輩出されず、作品をコレクションしているところも、欧米と比べると非常に少ない。「日本より、ドイツの方が制作を続けやすいのでは?」と周囲に提案されることも多かったという。
「僕も最初は、ドイツに残って活動を続けようと思っていました。マイスターシューラーを取得させてもらったという責任感もあり、ドイツのブックアート界を牽引していく存在になることも大事だと思いました。でもこの先、僕のようなマイスターシューラーが輩出されても、日本でいちから土壌を作り、ブックアートを広めていけるのは日本で育って日本のことを理解している僕しかいないんじゃないかと思ったんです」。
また、太田さんは日本にブックアートが根付くポテンシャルを感じていたのだそう。 最初に挙げたのは日本の製紙技術の高さだ。太田さんはドイツ滞在時も作品によって日本の紙を仕入れて制作に使用していた。そんな作品制作における「環境の良さ」に加えて、日本に感じた可能性がもう1つあったという。
「日本は、場所がなくてアートを買う習慣がなかったり、作品の見方が分からないという人も多いじゃないですか。だけど、たとえ『絵画作品の良し悪しや見方がよくわからない…』という人でも、本の形をしたアートならきっと楽しめるんじゃないかと思ったんです。もし作品の深いコンセプトがわからなくても、『この本のこういう形を美しく感じる』とか『この紙の質感が好き』といった細部の美しさを感じて言葉にするのは、日本では得意とする感覚なのではないかと思いました。そういう意味で、日本的な感覚はブックアートにすごく合っていると感じました」。
そんなブックアートの魅力について聞くと、「いろんなアートの中でも要素が多いこと」と太田さん。


「Frucht Ⅲ」(2017)。トマトの「光沢感があるけどざらっとしている」手触りを表現するため、シルバーの紙の上に赤い色を刷っている。トマトの写真は太田さんが実際にスライスしハンドオフセット印刷したもの(写真提供:OTAブックアート)。
「ブックアートはテキスト、素材、印刷、製本などと細かく分かれたいろいろな要素があるというのが特徴。それゆえにいろんな入り口があるんです。作家がそれぞれいろんな武器を持っていて、イラストレーター、版画家、写真家が始めるということもあるし、編集者として本を考えることを入り口にブックアートを始める人もいます。武器によって特徴がいろいろ出てくるのが魅力ですね」。
全て分からなくても、自分が興味のある部分的な“要素”に注目して楽しめるし、そうやって見ているうちに他の要素も好きになるかもしれない。自分らしい視点で作品を楽しめるのも魅力の一つだ。
新たな挑戦の拠点となったアトリエへのこだわり

武蔵小山の住宅街を横道に入った先にアトリエがある
日本での活動をスタートした太田さんの拠点となっているのが、今回の取材場所でもある武蔵小山のアトリエ「OTAブックアート」だ。
日本でブックアートを広めていきたいという思いから、自身の制作場所としてはもちろん、ワークショップなどを開催できるような物件選びを意識したそうだ。
また、この規模のアトリエを持つことには、強い憧れがあったという。
「大学学部生の頃、デザイナーで思想家でもあるウィリアム・モリスの『理想の書物』に強く影響を受けたんです。なかでも、彼が晩年に作った工房のケルムスコット・プレスがすごく印象的で。僕も制作活動のシンボルとしてのアトリエを持ちたい、とずっと思っていました」。

アトリエには本づくりにまつわる道具が並ぶ。ここに並ぶアイテムは、オンラインショップ『OTAブックアート ショッピングセンター』で購入可能だ
木製の棚やフローリングの温もりから、どこか優しい雰囲気を感じるOTAブックアート。床はもともとコンクリートだったが、太田さん自身が手作業で床板を敷き詰めたそうだ。
「このアトリエは、ドイツにいた頃に使っていた工房が原点となっています。というのも、ドイツ時代の工房も、床や机などが全て木でできていたんです」。

窓際、アトリエの角にある太田さんの作業机。立って作業するため、高さは普通の机よりも高くなっている。
「当時、僕の作業机は工房の角にあったんですが、その壁際は僕のものだらけで(笑)。悪くいえば散らかっていたんですが、教授には『積極的に制作しているから自由に使っていいよ』と言ってもらっていました。日本に一時帰国してドイツに戻ったときにも、教授が『“Yashi-Ecke”(太田さんの呼び名である「Yashi」の角(=Ecke)という意味)を用意しておいたよ』と机を残しておいてくれて嬉しかったのを覚えています。その頃の感覚を残しておきたくて、このアトリエの角にも当時と同じ高さの机を置きました」。
本の可能性を追求する「OTAブックラボ」

「OTAブックラボ」第0期のラボミーティングの様子(写真提供:OTAブックアート)。
ブックアート文化の定着を目指して新たに始めたのが、「OTAブックラボ」だ。実際に作品づくりができるラボとして、2018年の秋に第0期が始動した。前例のないブックアートのラボに手探りで挑戦していくことを意識して、あえて『0期』としたのだそう。1年かけて1人1作品を作ることを目標とし、活動のメインは月1回のラボミーティング。チームごとに分かれてメンバーが集まり、制作プロセスを発表し合うというものだ
募集当初は人が集まるか不安だったというが、実際は、写真家や編集者、美大卒業生、主婦、遠方からなど幅広い人から応募があった。一方、続けていくなかで途中離脱する人も少なくなかったという。ブックアートの魅力である“要素の多さ”は、作り手にとっては必要な知識や技術の多さとなる。ドイツの芸術大学でも厳しい選考をくぐり抜けてきたにも関わらず挫折してしまう学生が何人もいたのだそう。
0期開始から1年が経ち(最終の作品発表はコロナウイルスの影響で現在延期となっている)、これまでの取り組みについて、太田さんは次のように振り返る。
「ラボでは、僕の作品とは全然違うものが出てきたらいいなと思い、参加者の方それぞれの経験や発想といった武器を活かしてもらうことを意識していました。製本を始めとした様々な技術は努力で身につけられます。それ以上にその人が何十年と生きてきたなかで仕上がってきた『個性』が大事だと考えています」。
そんな0期の活動をふまえ、始動したばかりのOTAブックラボ1期(2020年6月スタート)について、次のように意気込みを語る。
「ラボは継続することで意義がより深まっていくと思っています。0期から継続するメンバーと、1期から参加するメンバーとの間でどんな反応が起こるか楽しみですね。僕自身、0期での経験を活かして、より内容を深めていければと思っています」。
今後の目標についても聞いた。
「知ってもらう機会を広げることと、作品を深めていくことを継続していきたいです。例えば、先日のポーラミュージアム アネックスでの展示のように、和紙を使う人、セラミックを使う人の作品の中に“本”が入ることって数年前には想像もできなかったことなんです。やりたいと思ってもチャンスがなくて、10年前は考えもしていなかった。それがやっとできるようになってきたという感覚があります。本の世界も大事ですが、一歩出たとこで見てもらうのも意義があると思うし、これからそれがどう広がっていくかっていうのはすごく楽しみ。
年齢的にもキャリア的にも、これで完成形ではいけないので、今後も本の解釈をより深めてブックアートを追究していきたいです」。
冒頭で述べたように、2010年以降、本のあり方は様々な場で議論されてきた。これについて太田さんは、「ブックアートにおいては、チャンスだと思った」と語る。
「紙の本がなくなればいいという人がいれば、紙こそが良いという人もいます。大事なのはそういう視点が新しくできたこと。紙が当たり前じゃなくなったことはチャンスだと思いました。流通面や在庫、情報伝達の速さといった点で優れている電子書籍が、そういった紙の本の苦手な部分を担ってくれるなら、それぞれの得意なものを生かせて、本全体としては追究されますよね。ただ、ノスタルジックで安易な“いいじゃん”では結局またダメになってしまうと思うので、“いまこんな風にいかしたらもっと新しい価値を持つ”というところまで持っていけたらまた先に繋がっていくのではと思います」。
「電子書籍元年」から10年経ち、逆に電子書籍にできないことが見えてきたことで、紙にしかできないことに対する意識は上がってきている。電子書籍と紙の本という2分割で考える時代も終わりを迎えてきていると太田さんは話す。ただ単純に形があるかないかで判断するのではなく、本自体がなんなのかと考えること、それはまさにブックアートに対して太田さんが大切にしている視点だ。
「本とは何か?」を考えさせられると同時に、その表現の自由さに驚かされる太田さんのブックアート。「いろんな要素で作られるからこそ、作る側も見る側も、自分らしいアプローチで見てもらえれば」という彼の言葉を胸に、ブックアートの世界に触れてみたいと思う。
【取材/文:市川茜+『ACROSS』編集部・堀坂有紀】
YOUTUBEチャンネル『OTA BOOK ARTS』 https://www.youtube.com/channel/UCRXXBysyaFbfCY5VlR4PycQ
“OB-Talk”
太田さんがゲストと共に本について語り合うオンラインのトークイベント。 https://note.com/otabookarts