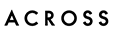* * *
「読書は私に新しい視点をくれる」
本を読めば、読むほどに不安になる。この世には知らないことが多すぎる。活字が私に与えてくれるのは、喜びはもちろんだが、自分や社会に対しての失望感や悲しみも多い。それでも、また本屋に行って新しい本を買うのは、文字を通して「他者」に触れることで、「他者」としての自分を見つめたいからだろう。
現代を生きる、ファッションデザイナーとして、常に自分(達)のクリエーションを「誰」に届けるのか、そして自分は「誰」なのかを問い続けている。社会のなかで発表する以上、肩書きがラベルのようにつきまとう。「20代」「日本人」「男性」「クリエーター」、それらを全て取り払って、匿名で表現できればいいのにと思うが、2020年代それは不可能に近い。
1人の人間として、「男性である自分」「日本人である自分」など、自分に貼られたラベルを通して、姿勢や行動一つが、誰かを不安にさせる可能性があると、意識するようになったのは読書を通してだ。もちろん、表現する人間としても、自分のラベルに対して無意識で生きることは許されない。
私が初めてフェミニズムを意識したのは、大学の卒業制作のリサーチの時だった。石内都の写真を通して、戦時中、広島の人々に生活を奪われた人々の声が届いた時、それまで意識していなかった、自分の中に孕んでいる暴力性や、育っていく中で植え付けられてきた、当たり前に、少しずつだけれど向き合っていこうと思った。「当たり前」が蔓延する世の中で、少しだけ視点を変えると、自分の間違えや愚かさに気づける。誰も傷つけずに生きることはできないけれど、それでもできるだけ正しく生きようとすることはできる。読書は、私に新しい視点をくれる。

イ・ラン『話し足りなかった日』リトルモア, 2021/イ・ラン『かなしくてかっこいい人』リトルモア, 2019
イ・ラン『話し足りなかった日』リトルモア, 2021
イ・ランの文章に初めて触れたのは2019年に日本で発行されたエッセイ集『かなしくてかっこいい人』(リトルモア, 2019)だった。ロンドン留学中の、短期帰国時、たまたま本屋で手にした。シンガーソングライターで、漫画家で、小説家の彼女の、生活とクリエーション、そこに含まれるお金や、性、家族のあり方などが綴られていた。韓国という、近くて遠い国の文学に触れたのもそれが初めてだった。性別も国も違うのに、文章から浮かび上がってくる生活の香りが、隣の家から届いてきているように感じた。
それから、この本は生活に迷った時、製作に疲れてしまった時などに、お守りのように何度も読み返す本になった。『話し足りなかった日』は、同じくエッセイ集で、2020年に韓国で発行されたものの日本版である。前作よりも、もっと彼女の周りの人々や社会との関係性、現在進行形での問題が生活の中でどのように滲み出てきているかが描かれている。イ・ランの文章は、私が毎日の生活の中で、目を瞑ってしまっている問題に、ちゃんと目を向けるように話しかけてくる。
・イ・ラン『話し足りなかった日』リトルモア, 2021
・イ・ラン『悲しくてかっこいい人』リトルモア,2019
それから、この本は生活に迷った時、製作に疲れてしまった時などに、お守りのように何度も読み返す本になった。『話し足りなかった日』は、同じくエッセイ集で、2020年に韓国で発行されたものの日本版である。前作よりも、もっと彼女の周りの人々や社会との関係性、現在進行形での問題が生活の中でどのように滲み出てきているかが描かれている。イ・ランの文章は、私が毎日の生活の中で、目を瞑ってしまっている問題に、ちゃんと目を向けるように話しかけてくる。
・イ・ラン『話し足りなかった日』リトルモア, 2021
・イ・ラン『悲しくてかっこいい人』リトルモア,2019

レベッカ・ソルニット『私のいない部屋』左右社, 2021/『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』左右社, 2021
レベッカ・ソルニット『私のいない部屋』左右社, 2021、
レベッカ・ソルニット『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』左右社, 2021
イ・ランの本に出会ってから、韓国文学やフェミニズムの本をよく読むようになった。それらの本を読むたびに、自分の中にある男性性やそれに付随する暴力性に嫌になってくる。ソルニットの本は、特に読んでいて辛くなる。自分が過去に犯してしまった過ちや、今もなお、気づかないうちに人に向けている差別的な視線や、見えない暴力に気が付いてしまうからだ。
「私のいない部屋」は、サンフランシスコで部屋を借りたソルニットが作家になるまでのエッセイである。フェミニズムの話だけでなく、環境問題や戦争など、社会の中で私たちが問題に向かって、彼女がどう向き合ってきたか綴られている。
かつてバージニアウルフが『自分一人の部屋』のなかで「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない」と書いたように、ソルニットやイ・ラン、多くの作家の部屋からの物語が、私の手元まで届いている。
「私のいない部屋」は、サンフランシスコで部屋を借りたソルニットが作家になるまでのエッセイである。フェミニズムの話だけでなく、環境問題や戦争など、社会の中で私たちが問題に向かって、彼女がどう向き合ってきたか綴られている。
かつてバージニアウルフが『自分一人の部屋』のなかで「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない」と書いたように、ソルニットやイ・ラン、多くの作家の部屋からの物語が、私の手元まで届いている。

滝口悠生『長い1日』講談社, 2021
滝口悠生『長い1日』講談社, 2021
2年前わたしも、自分1人の部屋を手に入れた。大きな窓のある、小さなメゾネットのアパートはデザイナーになって自分の稼いだお金で初めて借りた部屋だった。今年の夏、そこを引っ越した。「自分一人の部屋」だったその部屋は洋服を作る、自分たちの部屋へと変わっていった、そして自分たちには少し狭くなってきたからだ。
滝口の『長い1日』は小説家の夫婦が引っ越す物語である。日々の出来事の、語られる視点が徐々に入れ替わっていき、同時にそこに書かれている日々、徐々に交わってくる。同じく引っ越しをしているタイミングに、この本を読んだこともあって、自分の生活もこの小説の一部になっていくような感覚になった。
滝口の『長い1日』は小説家の夫婦が引っ越す物語である。日々の出来事の、語られる視点が徐々に入れ替わっていき、同時にそこに書かれている日々、徐々に交わってくる。同じく引っ越しをしているタイミングに、この本を読んだこともあって、自分の生活もこの小説の一部になっていくような感覚になった。
当たり前だが、自分の生活も、身近な人間の視点を通すと別の1日に見えてくる。徐々に沈んでいく太陽のように、別々の1日、別々の人間だろうと、ゆっくりと繋がっているのだと思った。
日々の読書を通して、遠くの生活が自分の生活と交わっていく。「他者」であるはずの作家、「他者」としての自分とほんの少しだけでも、分かり合えたような気分になれた時、自分たちの作り出した洋服もまた、そのように感じてもらえたら幸せだと思う。
(文:小林裕翔)
・ 滝口悠生『長い1日』講談社, 2021
(文:小林裕翔)
・ 滝口悠生『長い1日』講談社, 2021