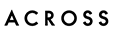2023年3月14日(火)14:00/大倉山記念館
毎シーズンユニークな会場をチョイスして記者たちを驚かせるpays des fées。今シーズンも独自路線を貫き、大倉山記念館内の、収容人数80人ほどという狭小なホールでショーを開催した。
コレクションタイトルの「Atbulae AnARTomicae」とは、アートワークを手掛けた画家・スズキエイミさんによる造語で、「絵画解体新書」の意。歴史的な解剖学書『ターヘル・アナトミア』を想起させるタイトルのとおり、「美しい遺体」のための衣装として構成されたコレクションである。
デザイナーの朝藤りむさんによれば、インスピレーション源となったのは即身仏(日本におけるミイラ)の皮膚や血管、筋肉の造形だという。無機質でありながら永遠の時を内包したそれに艶やかさを見出した彼女は、ベロアやチュールなどを用いて即身仏の皮膚を再構築。解剖図やミイラの手といったグラフィックも相俟って、ブランドらしい甘美でグロテスクなムードに仕上がっていた。
・オフィシャルサイト
・Instagram
pays des fées(ペイデフェ)

pays des fées/写真:ACROSS編集室
HARUNOBUMURATA(ハルノブムラタ)
2023年3月14日(火)15:30/グランドプリンスホテル高輪
2022AWシーズン以来のランウェイショーを開催したHARUNOBUMURATA。今シーズンはJERRY SCHATZBERG(ジェリー・シャッツバーグ)の写真集『WOMEN THEN』に大きくインスパイアされ、同写真集に収められている50〜60年代頃のディオールやイヴ・サンローランといったブランドのサロンショーのようなムードを演出するため、会場をグランドプリンスホテル高輪の「貴賓館」に決めたとデザイナーの村田晴信さんは語る。
ショーの序盤では黒一色のルックが続き、中盤以降はベージュやブルー、グリーン、終盤は白一色と徐々に色合いが移り変わっていく構成。シャッツバーグの写真さながらに、モノクロの世界に差し込む光をスワロフスキーのフリンジアイテムで表現した。
片方だけ立てた襟掴んだり、ポケットに手を入れて少しだけブレスレットを覗かせたりと、細かい動きや振る舞いの中に美しい瞬間を散りばめて、クラシカルで王道のエレガンスのなかに物語性を潜ませた。「パリのエレガンスを日本でそのまま表現しても仕方ない。そこにどうやって現代性を加えていくかを考えている」(村田さん)という。
日本のブランドならではの要素としては、やはり素材づかいのユニークさ。たとえばわざと何度も毛羽立たせることでカシミアのような質感を与えた繊細なシルクのケープコートや、膨れ織ジャカードのシルクオーガンジーで作られたダウンジャケットなどがその象徴的な存在だった。
2022AWシーズン以来のランウェイショーを開催したHARUNOBUMURATA。今シーズンはJERRY SCHATZBERG(ジェリー・シャッツバーグ)の写真集『WOMEN THEN』に大きくインスパイアされ、同写真集に収められている50〜60年代頃のディオールやイヴ・サンローランといったブランドのサロンショーのようなムードを演出するため、会場をグランドプリンスホテル高輪の「貴賓館」に決めたとデザイナーの村田晴信さんは語る。
ショーの序盤では黒一色のルックが続き、中盤以降はベージュやブルー、グリーン、終盤は白一色と徐々に色合いが移り変わっていく構成。シャッツバーグの写真さながらに、モノクロの世界に差し込む光をスワロフスキーのフリンジアイテムで表現した。
片方だけ立てた襟掴んだり、ポケットに手を入れて少しだけブレスレットを覗かせたりと、細かい動きや振る舞いの中に美しい瞬間を散りばめて、クラシカルで王道のエレガンスのなかに物語性を潜ませた。「パリのエレガンスを日本でそのまま表現しても仕方ない。そこにどうやって現代性を加えていくかを考えている」(村田さん)という。
日本のブランドならではの要素としては、やはり素材づかいのユニークさ。たとえばわざと何度も毛羽立たせることでカシミアのような質感を与えた繊細なシルクのケープコートや、膨れ織ジャカードのシルクオーガンジーで作られたダウンジャケットなどがその象徴的な存在だった。

HARUNOBUMURATA/写真:オフィシャル提供
ablankpage/AS YEARS GOES BYS ABLANKPAGE X EDWIN(アブランクページ/アズ イヤーズ ゴーズ バイズ アブランクページ × エドウィン)
2023年3月14日(火)20:00/渋谷ヒカリエ ヒカリエホールA
先シーズンに続いて2度目の東京コレクション参加となった、バンコク出身のラロパイブン・プワデトさんによるablankpage。今シーズンは、デニムブランドのEDWINとコラボレーションし、なおかつゲストデザイナーに石澤駿を迎えたAS YEARS GOES BYS ABLANKPAGE X EDWINとの合同ショーという形式で発表した。
バンコクと東京というデザイナー自身のルーツにあらためて向き合った先シーズン。今シーズンはよりデザイナーのパーソナルな内面にフォーカスし、自作のボードゲームで従兄弟と遊んでいた彼の幼少期の記憶からデザインがはじまったようだ。オリジナルのグラフィックは今まで以上にポップかつキュート。子どもが大人の服を着たときのサイズ感をトレースし大きめに仕立てられたジャケットは、大人へと変化していく自身の心境のメタファーだという。
一方のAS YEARS GOES BYS ABLANKPAGE X EDWINは、EDWINから提供された不良品等の素材を用いて製作されたSDGsを意識したプロジェクト。前回の東京コレクションでも、RAGTAGとコラボレーションしたREQUAL≡や、元CHRISTIAN DADAの森川さんによる環境に配慮したブランドBASICKSなど、いわゆるSDGsっぽいアプローチが目立ったが、ファッションウィークを上げての取り組みはまだこの先も続きそうだ。
先シーズンに続いて2度目の東京コレクション参加となった、バンコク出身のラロパイブン・プワデトさんによるablankpage。今シーズンは、デニムブランドのEDWINとコラボレーションし、なおかつゲストデザイナーに石澤駿を迎えたAS YEARS GOES BYS ABLANKPAGE X EDWINとの合同ショーという形式で発表した。
バンコクと東京というデザイナー自身のルーツにあらためて向き合った先シーズン。今シーズンはよりデザイナーのパーソナルな内面にフォーカスし、自作のボードゲームで従兄弟と遊んでいた彼の幼少期の記憶からデザインがはじまったようだ。オリジナルのグラフィックは今まで以上にポップかつキュート。子どもが大人の服を着たときのサイズ感をトレースし大きめに仕立てられたジャケットは、大人へと変化していく自身の心境のメタファーだという。
一方のAS YEARS GOES BYS ABLANKPAGE X EDWINは、EDWINから提供された不良品等の素材を用いて製作されたSDGsを意識したプロジェクト。前回の東京コレクションでも、RAGTAGとコラボレーションしたREQUAL≡や、元CHRISTIAN DADAの森川さんによる環境に配慮したブランドBASICKSなど、いわゆるSDGsっぽいアプローチが目立ったが、ファッションウィークを上げての取り組みはまだこの先も続きそうだ。

ablankpage/写真:ACROSS編集室
SOSHIOTSUKI(ソウシオオツキ)
2023年3月14日(火)21:00/TOKYO FMホール
麹町のTOKYO FMホールを舞台にショーを開催したSOSHIOTSUKI。2016AWシーズンに「東京ニューエイジ」として合同ショーを行って以来、単独としては初のショーだ。
真っ暗なホールに高らかな警報音が鳴り響き、ショーの幕が開く。薄暗い照明にわずかに照らされたのみのランウェイを、猫背のモデルたちが次々と足速に歩き去っていく。
大月さんの作品でいまでも鮮烈に記憶に焼き付いているのは、2013年に渋谷パルコで開催された「絶命展」(あるいは翌年の「絶・絶命展」だったか)で見た、黒い糸でゴキブリが刺繍された喪服のようなテーラードジャケットだ。靴底をすり減らして働く高度成長期の男たちのペシミズムを現代的なダンディズムに昇華した、日本特有のマスキュニティを炙り出した展示にとにかく衝撃を受けた。その後彼の創作のテーマが旧日本軍へと移り変わっていったのも、原点を思えばごく自然なことに映った。
大月さんがまだ学生時代だった2013年に制作した最初のコレクションタイトルは「FINAL HOMME」。今シーズンのコレクションタイトルは「FINAL HOMME2」ということで、10年の年月を経たいまも、創作の根底に流れているものは変わらないのだろう。所謂「ドブネズミスーツ」のようなグレーのスーツや、葬列を思わせる黒いルックの連続。死装束のような真っ白のルック、遺影にかける黒いリボンのようなネクタイ。さらにKOTA OKUDAとのコラボレーションで制作した百円紙幣柄のTシャツや数珠風のネックレス、あるいは山陽山長のシューズなどによって、「日本性」は強化/反復され、より一層強固なものとして見る者の意識に入り込んできた。
ショーの冒頭から身体中に走った息を呑むような緊迫感は、翌朝になってもまだ残り続けているほどだった。
・Instagram
麹町のTOKYO FMホールを舞台にショーを開催したSOSHIOTSUKI。2016AWシーズンに「東京ニューエイジ」として合同ショーを行って以来、単独としては初のショーだ。
真っ暗なホールに高らかな警報音が鳴り響き、ショーの幕が開く。薄暗い照明にわずかに照らされたのみのランウェイを、猫背のモデルたちが次々と足速に歩き去っていく。
大月さんの作品でいまでも鮮烈に記憶に焼き付いているのは、2013年に渋谷パルコで開催された「絶命展」(あるいは翌年の「絶・絶命展」だったか)で見た、黒い糸でゴキブリが刺繍された喪服のようなテーラードジャケットだ。靴底をすり減らして働く高度成長期の男たちのペシミズムを現代的なダンディズムに昇華した、日本特有のマスキュニティを炙り出した展示にとにかく衝撃を受けた。その後彼の創作のテーマが旧日本軍へと移り変わっていったのも、原点を思えばごく自然なことに映った。
大月さんがまだ学生時代だった2013年に制作した最初のコレクションタイトルは「FINAL HOMME」。今シーズンのコレクションタイトルは「FINAL HOMME2」ということで、10年の年月を経たいまも、創作の根底に流れているものは変わらないのだろう。所謂「ドブネズミスーツ」のようなグレーのスーツや、葬列を思わせる黒いルックの連続。死装束のような真っ白のルック、遺影にかける黒いリボンのようなネクタイ。さらにKOTA OKUDAとのコラボレーションで制作した百円紙幣柄のTシャツや数珠風のネックレス、あるいは山陽山長のシューズなどによって、「日本性」は強化/反復され、より一層強固なものとして見る者の意識に入り込んできた。
ショーの冒頭から身体中に走った息を呑むような緊迫感は、翌朝になってもまだ残り続けているほどだった。

SOSHIOTSUKI/写真:オフィシャル提供