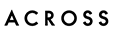「日本の地方でも、1年のうち364日はしっかり働いて、そこで得られた富を一日のお祭りに全て注ぎ込む、というマインドはまだ残っていますが、都会から離れた場所でこうしたお祭りをやることで、自然からもらっているものの大きさを大事にしたいという気持ちはありました。それと、運営やスタッフ、それにお客さんが与えてくれるもの。これも大きい。そして一番大きなギフトだと思っていたのは、子どもたちの存在ですね」(淵上さん)。
たしかに子どもは世界への贈りものだ。会場で一番驚いたのは、子どもの多さ。ほとんどが家族連れで、3歳以下の子どもたちが100人、小学生以下の子どもたちも100人くらい。1泊2日のキャンプをするのは少し躊躇するくらいの小さな子どもたちも多かった。バンガローは10張り前後で、後はみなテントで、はじめてキャンプをした人も少なくなかったようだ。
来場した人からは、「子どもたちが会場内を動き回ったり、隣のテントのテリトリーにもなんの気兼ねもなく入ってくるので、隣通しの垣根が下がって面白かった」という声もあった。子どもを通して親同士が友だちになりやすい、ということは町でもよくあることだが、山のキャンプ場のお祭りという日常とは違う空間では、より自然にそのような状況が発生していたようだ。すこし緊張も手伝って町の論理を持込みがちな大人の意識を尻目に、子どもたちは軽やかにその境界や分離を乗り越えていた。
「そういうことも含めて、“新しい村”をつくる実験をいろいろしたという感じですね」(淵上さん)。
“新しい村”のカタチがおぼろげに出現していたかもしれない、そんな予感を感じる新しいイベントだった。
【取材・文: 新村創 】