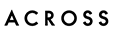2015年3月31日、同性カップルに対して「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行する「同性パートナーシップ条例」が東京都渋谷の区議会本会議で可決、成立したというニュースが大きな話題となった。この条例は法的な拘束力こそ持たないものの、日本の行政が同性カップルを認めたということでは歴史的な一歩だったといえよう。
そんな渋谷区の表参道エリアに“ゲイカルチャー”、“アートなセクシャリティ”、“多様性”をキーワードに据えたカフェ「gossip(ゴシップ)」がオープンしたのは、2010年のこと。2010年というとまだ渋谷区の条例が議会で提案されてすらいない頃だ。代表のタキタリエさんは、以前務めていた外資系の金融機関を退職した後、少しの準備期間を経て「gossip」をオープンした。

「会社を辞めた後、きっといろんな人の間で「タキタさんって転職したらしいよ」、「なんか店を始めたらしい」、「ゲイの店だって…」みたいに、ゴシップ(gossip)のようになりますよね。それを言われたら嫌だとネガティブにとらえるのではなくて、ちょっと面白い感じでポジティブなものとして受け止めたくて、そのままゴシップという店名にしました」とタキタさん。
そもそもこのような場所をオープンしようと思ったきっかけは、地方に住むLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の若い人たちの多くが自殺を考えたり、実際に行動に移してしまったりしているというニュースをメディアで見かけたことだったという。
「自身のセクシュアリティが原因で自殺してしまうなんて本当にもったいないと思い、原因は何だろうと考えました。もちろんいじめや親の理解がないということもあるのですが、やっぱり将来が見えづらいというのがいちばんの理由ではないでしょうか。なぜ将来が見えないかというと、彼らの周りに同じような人がいないから。いまでこそマツコ(マツコ・デラックス)さんやブルボンヌさん、小雪(東小雪)さんと裕子(増原裕子)さんなど、いろんな人がメディアに出ているけれど、当時はそれほどではありませんでした。それに、みんながみんな二丁目(新宿二丁目)のような場所に行けるわけじゃない。本当はメディアや二丁目のような特殊な場所にだけでなく、区役所にだって警察署にだって八百屋にだってLGBTの大人たちがたくさんいるのに、それが見えてこないから将来を悲観してしまうのではないでしょうか」(タキタさん)。
そんな悩んでいるLGBTの人たちのために、二丁目ではない場所にコミュニティスペースではない場所を作る必要性をタキタさんは感じ、「gossip」を開店することを決めた。
たしかに、二丁目以外の場所で「LGBTフレンドリー」であることを明言する店はほとんど見かけない。たとえば、『Time Out Tokyo』(2015年5月6日)の特集「東京、LGBTフレンドリースポット10選」で取り上げられた店の10店中8店が二丁目とその周辺にある店だった。
「二丁目を否定するようなつもりは全くありません。でも、やっぱりそういう特化した場所には行きづらいという人もいるんです。お酒が飲めない人や、あそこに行ったらゲイやレズビアンなんじゃないかと思われるのが嫌で行けないという人もたくさんいます。当事者の人もそうでない人も普通にいられて、その人のセクシュアリティがわからないような店、それでなおかつ昼間からやっていて、コーヒー一杯だけでも飲みに来られるお店にしようと思いました」(タキタさん)。

「gossip」では「NOZY COFFEE」のシングルオリジンコーヒーを提供している。他に各種アルコールも取り揃えられており、昼夜を問わず好きなドリンクを楽しむことができる。

ランチは肉と野菜のメニューがある。夜もパスタなどの軽食メニューが豊富。
LGBT当事者たちにとって意味のある場所であり、なおかつ当事者以外の人々も普通に入れるよう、LGBTフレンドリーだがそのことを前面に押し出さず、店頭にレインボーフラッグを掲げる程度にしたそうだ。

現在はレインボーフラッグの代わりにボードが設置されている。
当事者とそうでない人とを結ぶキーワードのひとつが“ゲイカルチャー”だ。店内にある巨大な本棚には三島由紀夫やトーマス・マンなどの小説、ヘルムート・ニュートンやロバート・メイプルソープなどの写真集、さらにはジェンダーやセクシュアリティ関連の書籍や雑誌などがぎっしりと並んでいる。だがどの本もエロやグロの類ではなく、写真集は性器が映っていないもの、小説は文学として評価されていて、昔から同性愛が文学のテーマになっていたということがわかるようなものが選ばれている それは、「未成年の人にも来てもらいたいし、その親御さんにもそんなところに行ったら危ないというふうに思われたくない。当事者の人が親戚や友だちを安心して連れて来られるようにしたい」というタキタさんの思いが根底にあるからだ。ちなみにこれらの本は購入することもできる(貴重な雑誌は非売品)。

「女のコが好きな女のコ、女性を愛する女性」のための雑誌『Novia Novia』、FTM(性同一性障害の一種)マガジンの『Laph』なども販売されている。ゲイ向けライフカルチャー誌の『ISmagazine』は閲覧のみ。

『仮面の告白』、『ヰタ・セクスアリス』、『草の花』、『孤島の鬼』、『ヴェニスに死す』…。同性愛をテーマのうちに含む小説の数々が本棚には並ぶ。

『imago』、『ユリイカ』、『クィア・ジャパン』など、貴重な雑誌のアーカイブも充実している(非売品)。
「gossip」の顧客は多種多様だ。店のコンセプトを全く知らない通りすがりの人も訪れるし、ネットで検索してやって来る人もいる。LGBT関連のオフ会に利用する人もいるし、店頭にある“We speak English”の文字を見かけて入店する外国人観光客もいる。そして東京でパレードや東京国際ゲイ・レズビアン映画祭が催される期間には、地方からの来店客も少なくないそうだ。ときには親しくなった人が親を連れて来たり、「子どもがLGBTなので勉強したい」という親が来店したりするそうだ。
店内には、来店者が自由にコメントすることができるノートが置かれている。これは、来店者同士が繋がるための重要なツールだ。気軽に一言だけ書き残していく人や来店するたびに毎回何か書いていく人、中にはページを埋め尽くすほどの文章を綴っていく人もいる。

ノートの表紙に描かれたオリジナルのロゴはテレビや人の口を象った“g”で、“gossip”という単語を連想させる。また、漢字の“口”とアルファベットの“g”が組合わさったような見た目は多様性を表現している。
「私たちが何かをするのではなく、ノートを通して「いろんな人がいるんだ」ということがわかればいいんです。実際に会ったことがなくても、このノートを見て「ひとりじゃないんだ」と思ってくれたらそれでいい。「ふたりの記念日に来ました」とか、「ここで出会いました」とか、すごくパーソナルなことを書いてくれる人が多くて、ここまで書いてくれるんだと驚きました。このノートはとても大切。家宝みたいなものです」(タキタさん)。
オープンしてから間もなく5年目を迎える「gossip」。今後はもっと多くの人にお店のことを知ってもらいたいとタキタさんは話す。

代表のタキタリエさん。
「最初はそんなこと思っていませんでしたが、店の存在を知ることで少しでも安心できる人がひとりでも増えたらいいなと思っています。当事者とそうではない人がカルチャーを通して境界なく接することができる、ハブのような場所を目指したいです」(タキタさん)。
現在セクシャルマイノリティが日本の人口に占める割合は、約5〜7%ほどと言われている。電通ダイバーシティ・ラボが実施した「LGBT調査2015」では、調査対象である20〜59歳の個人69989人のうちの7.6%が、LGBTを含む性的少数者に該当するという結果だった。同じ調査は2012年にも実施されており、当時は5.2%。この3年で約2.4%増加した。
5〜7%という数値はたしかに少数かもしれないが、たとえば総務省が5年ごとに実施している「社会生活基本調査(2011年)」の15歳以上のサッカー競技人口約4.5%、野球競技人口約6.2%(プロ選手は除く)などと比較すると、決して珍しい存在を示すものではないことがわかる。にもかかわらず、数多ある人間の差異の中でセクシュアリティだけが大げさに扱われるのはなんとも奇妙なことだ。
LGBTをめぐる人権問題は現在、世界中で議論の対象となっている。特に同性婚については、2015年5月にはアイルランドで、6月にはアメリカのすべての州で合法化が決まったというニュースが記憶に新しい。こういった変化に比べれば日本の変化は小さなものかもしれないが、渋谷区に続き、8月、世田谷区も同性カップルに対して公的書類を発行することを決定した(渋谷区と異なり条例ではない)。また現在、横浜市や宝塚市でも同様の議論がなされているそうだ。
少しずつ風向きが変わりはじめた状況下で、日本の各地に「gossip」のような場所が増えていくのかどうか、これから注目したい。
[取材/文:大西智裕(ACROSS編集部)]