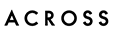「パリで60万人が熱狂!」のコピーにポップなタイポグラフィ、赤毛の女性アーティストがこちらに銃口を向けるピンクの展覧会チラシ。「ちょっと気になる」と思って手にした女性も少なくないのでは。
国立新美術館で開催中の「ニキ・ド・サンファル展」はそんな女性たちが訪れ、気になる何かを見つけていたような展覧会だった。
ところで、ニキ・ド・サンファルって誰?という人も多いのではないか。ニキは1930年にフランス生まれ、抽象画やパフォーマンスアートが注目され、その後解放的な女性を表す「ナナ」シリーズが人気を博すなど、多くの絵画や造形作品を残した。晩年も彫刻庭園などを手がけ、2002年に71歳で亡くなるまで制作を続けた戦後を代表する美術家、である。巨大で丸っこくてカラフルなおばさんの像の人、という印象は強いが、この作家の全体像や作品評価はあまり日本では目にしたことがない気がしていた。


同世代の現代アート作家というと、ウォーホールやリキテンシュタイン、ジャスパー・ジョーンズなどなど大御所がたくさんいるけれど、その文脈の展覧会でもあまり見かけないし。今回の展覧会は、2014年秋にパリのグラン・パレで開かれた大規模な回顧展「ニキ・ド・サンファル展」が、2015年春のスペインのビルバオ・グッゲンハイム美術館に巡回、ニキの生誕85年目に合わせて日本独自の構成で開催されることになったのだという。
冒頭の「60万人が熱狂!」はパリでの回顧展のことで、たまたまその時期パリを訪れたアクロス編集長はものすごい行列で入れなかったそうな! 世界的に再評価の機運が高まっている作家なのだった。今、人気がある理由って、なんなのだろう。太っちょな女の子がブームだから、とか?
*パリでの展覧会の動画 http://youtu.be/XDfQUnLw8dc

展覧会は年代順に構成されていて、作家の人生と時代そのものを辿っていくようだった。その人生とは。
「11歳の時に父親から性的虐待を受けた少女は、1940年代に反逆する女性となり、50年代には前衛的なアーティスト、60年代にはメディアを利用する有名アーティスト、そして70年代にはパブリック・アートに取り組み、さらには常に女性に関わるものを含んだ様々な信条に携わるアーティストとなったのである」(カミーユ・モリノー:展覧会監修/展覧会図録より)
少女期の悲惨な体験から早くからフェミニズムに目覚め演劇、モデル、音楽家との結婚、出産、精神疾患などの末、絵やコラージュなどの制作をすすめられ作家活動にはいり、それが自分自身の解放の手段となっていく。ちょうどボーヴォワールの『第二の性』が発行された頃で、これに刺激され、女性の抑圧やステレオタイプのイメージに対抗する作品が多く生まれた。
魔女、聖母、娼婦など複数の顔を持ったり身体の一部が欠損した女性像、女性抑圧の象徴とみなすキリスト教会を銃で撃つ「射撃絵画」など、初期の作品は過激だ。東西冷戦や核への恐怖から、核実験により生まれた「ゴジラ」をモチーフにするなど、時代に敏感に反応している。
夫と子どもと別れ、新しいパートナーとともにアートを極める道に進んだのも、女性の自由な生き方の象徴のようだ。ふくよかな女性像「ナナ」シリーズが生まれたのもこのころからだ。カラフルな色使いはヒッピー文化に通じ、黒人女性は公民権運動への共鳴のあらわれ。巨大なナナの性器から中に入るという作品「ホーン」は、ウーマンリブ運動とも呼応しているようだ。
もしかして当時は過激だったり、物議をかもしていたかもしれないこれらの作品を、日本の観客は楽しそうに見ていた。会場にいたのは多くが女性、年齢層は比較的高い。母親と娘という組み合わせも見られた。母世代は作品が生まれた時代に青春時代を送ったり、もしかしたら結婚や仕事などで、ニキと同じように抑圧を感じたこともあったのかもしれない。
インタビュー映像でニキは「私は世界は変えられないけど、道を提示することはできる」「女性と黒人が世界を動かしたらきっとよくなるのに」と語っていた。作品を見ている彼女たちがその時代に聞いたら賛同しなかったかもしれないが、今なら大いに共感するだろう、娘も共に。50年以上前の女性アーティストの表現が、ようやく大勢の女性に受け入れられるようになったことが、今の再評価としてのあらわれなのかもしれない。
[取材/文:宮川真紀(タバクックス代表)]
ニキ・ド・サンファル展
NIKI DE SAINT PHALLE展
2015年9月18日(金)~12月14日(月)
※障害者手帳をお持ちの方の介添者(1名まで)は無料